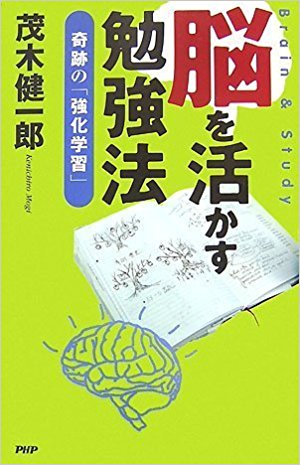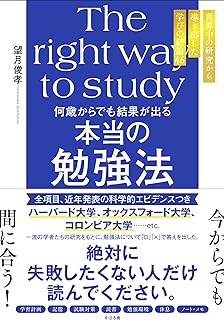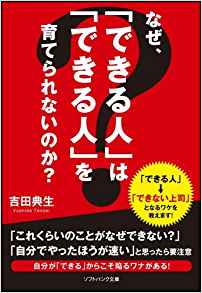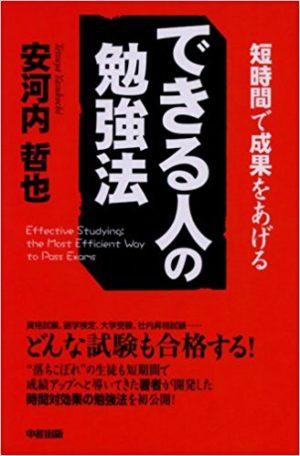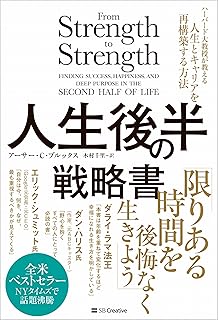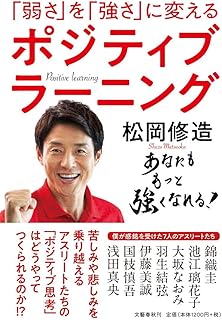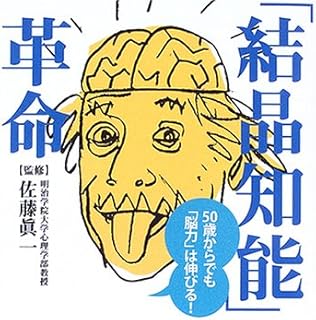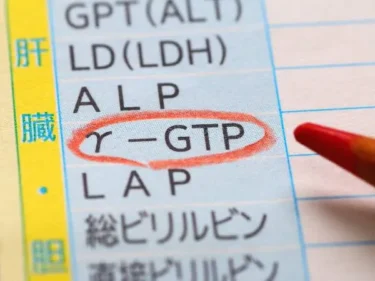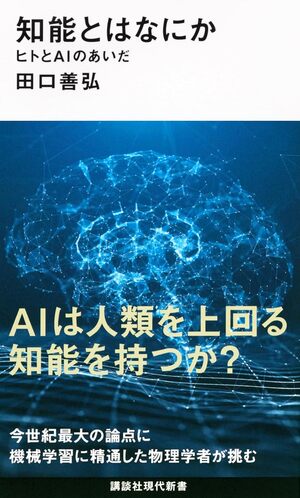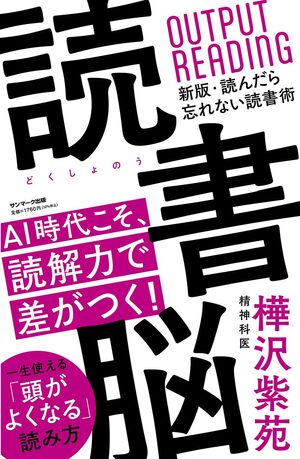- 本書の考える地頭力は、「発想力」「論理的思考力」「共感力」の3つで構成されている。ノート術を通して、ビジネスに欠かせないこの3つの力を鍛えよう。
- 「スタンフォード式超ノート術」では、必要な場面に応じて、「アイデア・ノート」「ロジカル・ノート」「プレゼン・ノート」の3種類を使い分ける。
- ノートでできあがったアイデアを行動に移し、ビジネスの課題解決をしていくことも非常に重要だ。創造性と生産性が掛け合わさることで、成果を最大化することができる。
スタンフォードで教えている最先端のノート術
地頭の良さを構成する3要素
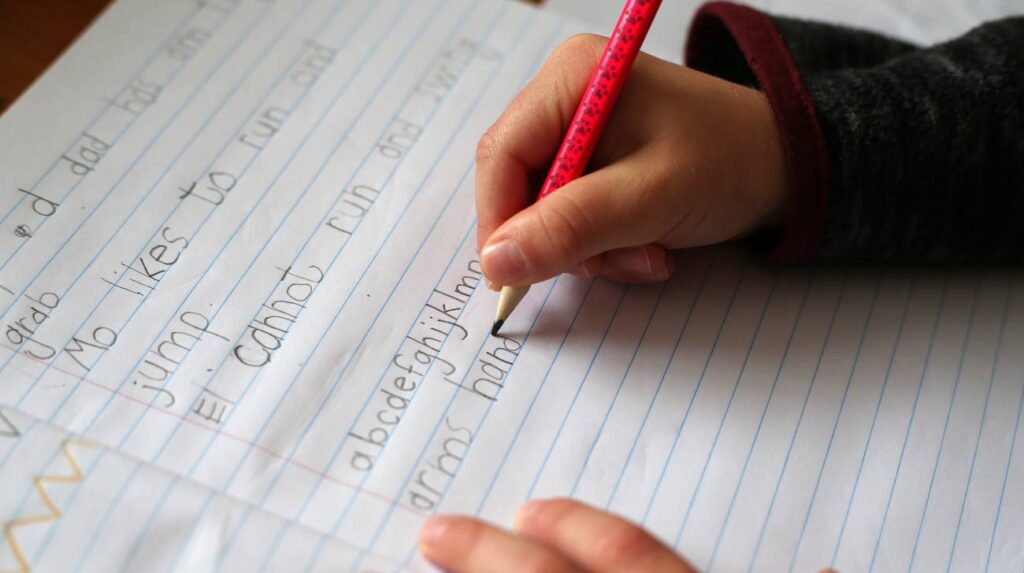
「地頭力」は「発想力」「論理的思考力」「共感力」の3つの要素から構成されています。
現代では「デザイン思考」という新しい手法の登場により、誰でも革新的なアイデアを生み出す「発想力」を向上させることが可能になりました。情報が急速に変化する現代社会では、じっくり時間をかけて正解を求めるよりも、変化に対応して新しいことに挑戦する「発想力」がますます重要になっています。
アイデアを生み出した後は、そのアイデアの長所と短所を見極める「論理的思考力」が必要です。この過程を経ることで、思考プロセスの再現性が高まります。
さらに、ビジネスの現場では「コミュニケーション能力」が不可欠です。どんなに正しい理論を持っていても、相手から「良いと思うけど協力したくない」と言われたら意味がありません。相手の感情や考えを理解する「共感力」も、地頭力の重要な構成要素なのです。
勉強には、王道がある! 勉強ゼロ→ラ・サール高校→東大→司法試験合格→裁判官→弁護士になった「本物の勉強法」を公開! 勉強の成果は、「3つの力のかけ算」で決まる。①【感情】「やる気をコントロールする力」②【戦略】「計画を立てて継続する力」[…]
スタンフォード式超ノート術の全体像
ノートの取り方には様々な種類があり、それぞれの手法を適切に使いこなせば効果的な結果が得られます。しかし、「この一つの方法さえマスターすれば必ず成功する」という万能のフォーマットは存在しません。重要なのは、一つの形式にこだわるのではなく、目的に合わせてノートの取り方を柔軟に変化させることです。
本書では、地頭力を高める3つのノート術を紹介しています。創造的な「アイデア・ノート」、思考を整理して分析する「ロジカル・ノート」、そして他者を動かす「プレゼン・ノート」です。これら3種類のノート法を組み合わせた「スタンフォード式超ノート術」によって、地頭力を構成する3つの能力を効果的に強化することができます。
基本のツールはシンプルに

スタンフォード式超ノート術の基本ツールは「付箋」「ノート」「ボード」という、シンプルで入手しやすいものばかりです。特別な高額アイテムや複雑な準備は必要ありません。
付箋は個人利用なら50mm四方か75mm四方が扱いやすいサイズです。一枚には約15文字程度と、詳細を書き込むよりも簡潔さを重視しましょう。3色ほど用意すると、人やテーマ別に色分けができて便利です。例えば著者は「過去」「現在」「未来」という時間軸で思考を整理するため、色分けした付箋を活用しています。カラフルな色使いは視覚的な刺激も生み出します。
ノートに関しては、形式やブランド、サイズに特別な制約はありません。自分の好みや携帯性を考慮して選びましょう。著者はA4サイズの書類を挟みやすいことから、基本的にA4ノートを使用しています。
ボードも重要なツールです。アイデア出しの場面では消去が簡単なホワイトボードが役立ちます。長期間同じテーマを考え続ける場合は、ボードに模造紙を貼る方法が効果的です。3Mのイーゼルパッドのようなホワイトボードに直接貼れる商品は、チームミーティングの効率化に貢献します。
脳は何かを達成するたびに、どんどん強くなる。 「喜び」がないと強化回路が回らない。大切なのはドーパミンによる強化回路が回るかどうか。 「突き抜ける」感覚はクセになる。できることを続けても脳は喜ばない。 苦しければ苦しいほ[…]
3種のノート術をマスターしよう
右脳を解き放つ「アイデア・ノート」
「アイデア・ノート」は、ビジネスの企画段階で活用できる発想力重視の右脳型ノート術です。量を重視し、アイデアを視覚的につなげていく手法です。
テーマからの脱線も歓迎します。右脳は本来「カオス」な性質を持つため、正しい思考の流れというものはありません。例えば、プレゼン資料作成中に「買い物リスト」が思い浮かんだら、それもノートに書き留めましょう。気になることをすべて書き出すことで、集中力を維持しながら発想を続けられます。
アイデアが次々と浮かび、手が追いつかず乱雑な文字になっても気にする必要はありません。「きれいに書こう」という意識は他者の視点を気にしている証拠です。他者の視点は一時的に忘れ、自分の思考を書き出すことに集中しましょう。
文字だけでなく絵も活用すると、右脳と左脳の両方が活性化し理解が深まります。あなた自身はもちろん、後でノートを見る人にとっても、文字と絵の組み合わせは情報の把握を助けます。
このノート法は「質より量」「失敗前提」が基本です。丁寧に作り込みすぎると、凡庸なアイデアでも「労力をかけたから」と執着してしまいます。多くのアイデアを生み出し、不要なものは躊躇なく捨てる気軽さが重要です。
やる気が出ない時でも、5~10分ほど作業を続けると「作業興奮」と呼ばれる脳の仕組みでスイッチが入ります。「今夜の夕食候補」「週末にやりたいこと」など身近なテーマから書き始め、まずは脳を活性化させることから始めてみましょう。
ニュートン・持続的な集中力・孤独の産物・孤独は天才の学校である。・生涯独身 サー・アイザック・ニュートン(英: (Sir) Isaac Newton、ユリウス暦:1642年12月25日 - 1727年3月20日、グレゴリオ暦:16[…]
「ロジカル・ノート」で優先順位を明確に

「ロジカル・ノート」は、アイデア・ノートで生まれた発想を分類し優先順位をつける、論理的思考力を重視した左脳モードのノート術です。
分析方法に迷った際は、2つの軸を組み合わせて情報を4つに整理するマトリクス法が効果的です。このとき重要なのが軸の選び方です。まず「事実」と「意見」で分けるのがおすすめです。「事実」は検証可能な正誤が存在するもの、「意見」は無数の選択肢があり検証が難しいものと定義できます。例えば「日本には47都道府県がある」は事実、「日本の都道府県は多い」は意見です。「ある商品の売上が年々減少している」という事実から「この商品は時代遅れだ」という意見を事実と混同してしまう誤りはよく見られます。事実と意見を明確に区別することで、思い込みを減らし判断の質を高められます。
「意見」はさらに「考え」と「気持ち」に細分化できます。「考え」は論理的・合理的で根拠があり、他者にも一定の納得を得られるものです。一方「気持ち」は感情的・情緒的で、人によっては共感を得られない場合もあります。
ロジカル・ノートでの分析をより深めるための思考法には3つあります。確からしい前提からアイデアを広げる「演繹的推論」、複数の事例から共通点を見出して一般化する「帰納的推論」、限られた事象からでも説得力のある仮説を立てる「アブダクション」です。これらを適切に活用することで、ビジネスコミュニケーションや意思決定の質を向上させることができます。
「できる人」が陥る三つの罠 その一 抜きん出た能力で頑張りすぎる罠その二 成功体験にもとづく信念の罠その三 高い常識がもたらす非常識の罠 「できる人」は、こうして組織をダメにする その一 仕事の目標だけで人を動機づけしよ[…]
仕上げは「プレゼン・ノート」
「プレゼン・ノート」は、アイデア・ノートやロジカル・ノートで形成されたアイデアや思考を、他者視点から再構築し共感を得られる内容に磨き上げるノート術です。問題発見から解決までのプロセスを体系化するために、「普段の様子」「課題や矛盾」「新しい提案」「日常の変化」を整理しながら「ストーリー・ボード」を作成しましょう。
このストーリー・ボードのフレームワークは「神話の法則」に基づいています。1949年、アメリカの神話学者ジョセフ・キャンベルが世界中の古典的物語を分析して導き出したこの理論によれば、「桃太郎」や「オズの魔法使い」のような時代を超えて愛される物語は、「旅立ち」「通過儀礼」「帰還」という3段階の展開パターンを持っています。このストーリー構造はプレゼンテーションでも非常に効果的です。
さらに説得力のあるプレゼンテーションを実現するには、左脳型の論理的「考え方」や右脳型の感覚的「感じ方」だけでなく、話し手の「信頼性」が不可欠です。信頼を構築する基盤となるのは相手への「共感」です。共感と似た感情に「同情」がありますが、同情は自分の経験と相手の経験を同一視し、相手の気持ちを推し量ろうとする行為です。一方、共感は自分の経験を脇に置き、相手の立場に立ってその苦しみを理解しようとする姿勢です。自分が経験したことのない事柄でも、相手の立場で考え理解しようとする「共感」ができれば、相手の興味・関心を深く把握し、相手が抱える理想と現実のギャップを埋める説得力のある話ができるようになります。
最初の一歩を踏み出す 「off the beaten track」から、新しい世界がはじまる。 誰もが「いつか~をやってみたい」と言うが、最初の一歩を踏み出せる人は少ない。最初の一歩を踏み出すには、「beaten track」[…]
もっとハイパフォーマーを目指そう
フロー状態を維持するコツ

アイデアをノートで発掘し、整理・分析して伝わる形に昇華させてきましたが、真の成果を生み出すには、構築したプランを実行に移し、仮説の妥当性を迅速に検証する必要があります。どれほど質の高いアウトプットをノート上で作成できたとしても、それが実際のビジネス課題を解決できるか、顧客ニーズに応えられるかは別次元の問題です。
ここで鍵となるのが、これまで解説してきた「創造性」と対になる「生産性」です。新たなWhat(何を)を見出す創造性と、それを最速で実現するHow(どうやって)を考える生産性。この二つを融合させてこそ、本当の成果が生まれます。
創造性と生産性には、それぞれ異なる特性とルールがあります。生産性の高い仕事を実現するには、高い集中力が生み出す「フロー状態」の維持が不可欠です。そのためには、少なくとも1時間ごとに10分の休憩を取ることが効果的です。調子が良いからと1時間以上作業を継続すると、反動で長期的な集中力が低下します。強制的にでも休息を取る方が、結果的に生産性が向上します。実際、1時間以上座り続けることは、喫煙と同等の健康リスクがあるとされています。
1日の取り組みタスクを3つまでに限定するのも効果的な戦略です。「今日は絶対に完了させる」項目をあらかじめ設定し、優先順位を明確にして達成していきます。一日の最初に何を完了させるかを意識するだけでも、生産性は大きく向上します。
まとめ
ートや手帳術に関心がある私は、雑誌特集や書店の新コーナーで注目の方法が登場すると、まずは試してみることにしています。「スタンフォード式超ノート術」の魅力は、右脳と左脳を意識的に使い分ける手法と、最終的なアウトプットから逆算して設計されている点にあります。また、美しく書く必要がないという明確な理由付けが、精神的な負担を軽減してくれます。書籍では、このノート技法が図解とともにより詳細に説明されています。