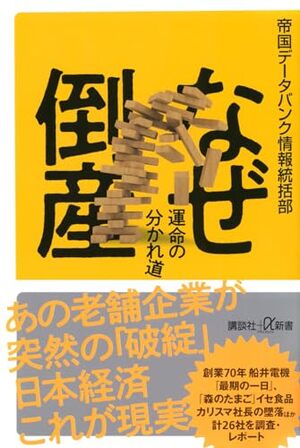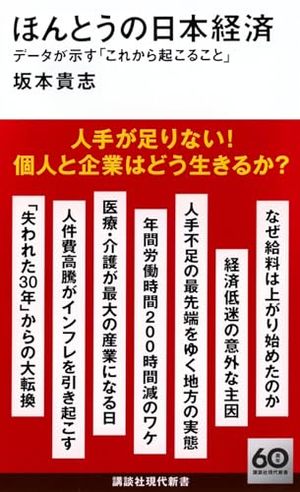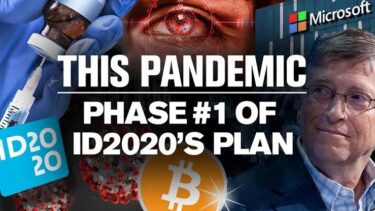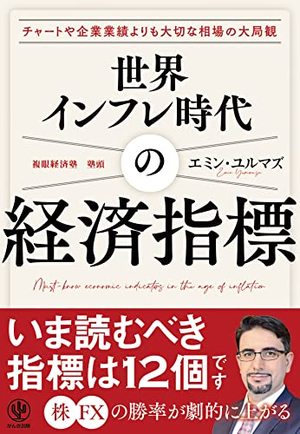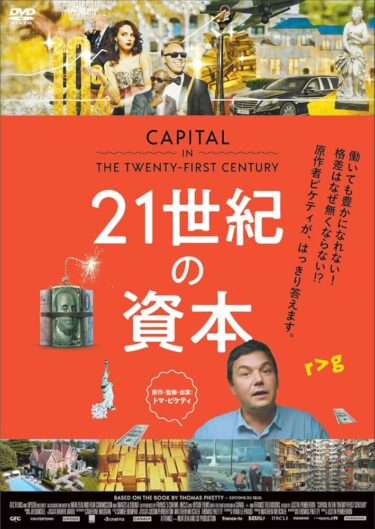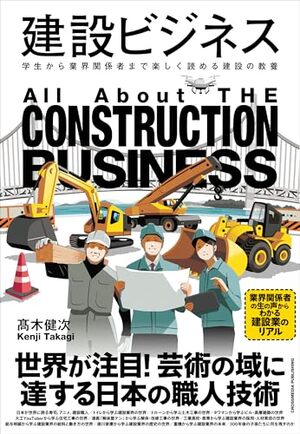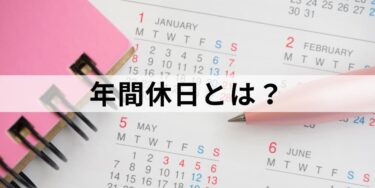- コロナ禍における支援策によって、本来破綻していたはずの企業も延命できていたが、支援終了とともに物価、人件費が高騰したことも相まって資金繰りに行き詰まる企業が増えたため、倒産件数が増加した。
- アフターコロナの倒産は、リーマン・ショック時のような「不況型」ではなく、資金面や人材確保の面で企業間格差が広がったことが原因となっている。
- 「ユニコーン」候補とされた企業や創業100年を超える老舗企業、大企業の事業を引き継いだ企業まで、経営環境の変化だけでなく、それぞれの個別の事情で倒産に至っており、一つひとつの事例を転ばぬ先の杖として学ぶことが大切だ。
企業倒産急増の背景と要因
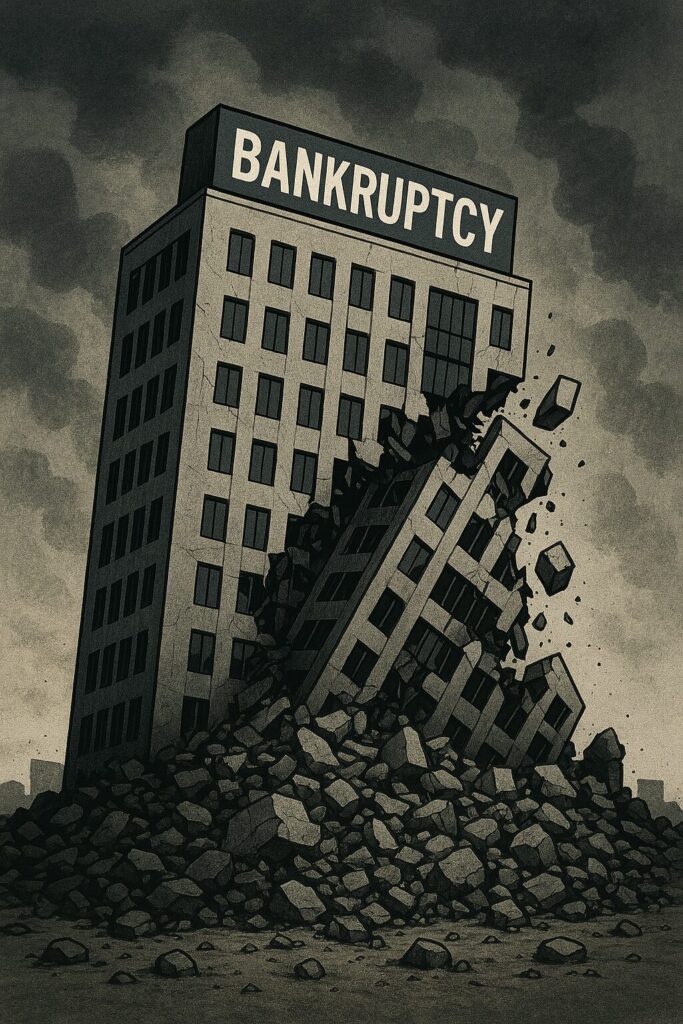
ポストコロナ時代の倒産の特色
新型コロナウイルスの世界的流行は、全球規模で経済活動に深刻な打撃をもたらしましたが、日本では政府による手厚い中小企業支援策により、倒産件数は一時的に抑制されました。行動規制の解除に伴い経済活動が再開されると、グローバルなインフレの波が押し寄せ、長期間続いたデフレからの転換点を迎え、「価格上昇と賃金増加の好循環を生む事業環境」が形成されつつあります。
ところが、中小・零細企業の倒産は再び増加傾向に転じています。この現象の背景には、以下の3つの主要な要因があります。
第一の要因:政府支援策の終了
コロナ禍で実施された総額約45兆円に及ぶ実質無利子・無担保融資(ゼロ・ゼロ融資)や休業支援金などの緊急支援策の段階的終了です。これらの支援により辛うじて経営を維持していた企業が、売上回復や返済計画の策定に至らないまま資金繰りに行き詰まり、業績改善を果たせずに保有資金を枯渇させるケースが頻発しています。
第二の要因:物価高騰による収益圧迫
支援終了と時期を同じくして本格化した物価高騰による企業収益の圧迫です。ロシアのウクライナ侵攻に起因する小麦粉・食用油の供給不安や半導体不足により、多方面でインフレ圧力が高まりました。さらに、日米金利差の拡大による円安が輸入価格の上昇を加速させました。賃金上昇が物価上昇に追いつかない状況下で、原材料価格の上昇分を販売価格に転嫁することが困難となり、収益改善を実現できない企業が経営破綻に追い込まれています。
第三の要因:深刻な人手不足
生産年齢人口の減少が進む中、賃上げ実現の困難さによる人材流出や後継者不在により、事業継続を諦める事例が増加しています。ポストコロナ期の倒産増加は、資金調達力と人材確保力における企業間格差の拡大によってさらに加速すると予想されます。これは、リーマンショック時の世界的需要減退による「景気後退型倒産」とは本質的に異なる性格を持っています。
設立間もないスタートアップから創業100年を超える老舗企業まで、倒産リスクは常に存在します。経済環境の変化、運不運、些細な経営判断の誤りなど、それぞれ固有の要因で行き詰まることがあります。こうした実例を詳細に分析し、予防策として活用することが重要です。
少子高齢化が進み人口減少経済に入った日本は、「人手を介したサービスへの需要」が高まる一方で、労働市場の需給がひっ迫し、深刻な人手不足に陥っている。 日本経済が低迷しているのは労働生産性の問題ではなく、労働投入量(総労働時間[…]
新興企業と老舗企業の倒産事例
太陽光発電事業の「ユニコーン」企業の失墜

新電力向けシステム開発を手がける「パネイル」は、電力自由化時代の基盤システムを提供する企業として、多くのメディアで注目された有望なユニコーン候補でした。名越達彦社長は学生時代に鳥人間コンテストで優勝した経験を持ち、株式会社ディー・エヌ・エーでモバゲーの立ち上げに参画した、エネルギッシュな経営者でした。
名越社長が展開した太陽光発電事業者の営業代行ポータルサイト運営や部材調達代行サービスは、2012年の固定価格買取制度(FIT)開始による太陽光バブルの恩恵を受けて会員数を拡大しました。しかし、このバブルが終息すると、これらの事業から迅速に撤退し、次の成長分野として新電力市場に参入しました。これは時代の流れを読む優れた経営感覚の表れでした。
電力需給管理基幹システム「パネイルクラウド」は、電力需給のビッグデータをAI分析し、電気料金請求の自動処理までをクラウド上で実現すると宣伝されました。2016年4月の電力小売全面自由化に完璧にタイミングを合わせてリリースされ、株式上場を視野に入れた同社は日本発のユニコーン候補として脚光を浴びました。
しかし、2018年9月期以降、決算情報の開示が停止され、1年以上経過後の決算公告で大幅な業績悪化が判明しました。この事態の原因は何だったのでしょうか。新電力の黎明期において「パネイルクラウド」は高い注目を集めましたが、実際の導入には結びつきませんでした。パネイルは同時に自社での電力小売業への参入を進め、全国に地域販売会社を設立していました。ところが、2018年初頭の電力価格高騰により、市場からの電力調達に依存していた同社は巨額の損失を被りました。これは、高精度の解析・予測機能を備えるはずの「パネイルクラウド」の信頼性を著しく損なう出来事でした。
期待されたユニコーン候補企業の倒産事例では、代表者がプレゼンテーションで自信満々に成長戦略を語る一方で、信用不安が拡大すると債権者に対して不誠実な対応を取るという、よく見られるパターンがあります。華々しくユニコーンともてはやされ、周囲が作り上げたサクセスストーリーに踊らされるのではなく、より堅実で着実な成長を追求すべきだったのではないでしょうか。
脱炭素についての議論がますます活発化していますが、その裏には意外な事実が隠されています。本記事では、脱炭素ビジネスの実態や利権争いについて探っていきます。脱炭素ビジネスの怪しい実態とは環境問題への意識の高まりと共に、脱炭素ビジネスが急速に[…]
再生可能エネルギー発電促進賦課金(以下、再エネ賦課金)は、再生可能エネルギーの普及促進を目的として、電力会社が再エネ電力を買い取るための費用を、電力消費者が負担する制度です。正式名称は「再生可能エネルギー発電促進賦課金」で、固定価格買取制[…]
撤退時期を見誤り事業承継に失敗した老舗経営者

鶏卵大手イセ食品グループの中核企業イセ食品は、1912年に富山で創業された「伊勢養鶏園」をルーツとする老舗企業でした。創業者の伊勢多一郎氏は年間365個の卵を産む鶏の品種改良によって事業を成功に導き、その息子の伊勢彦信氏がアメリカの養鶏技術導入などにより企業規模を拡大しました。年商200億円超の規模に成長後、アメリカに進出し、1984年には卵の販売量で全米首位を獲得しました。その後も中国、インド、アジア各国へと海外展開を推進しました。
企業収益の一部を芸術文化支援に充てる「メセナ活動」が当時のアメリカでブームとなっていたことも影響し、彦信氏はグループ会社の資金でイセ文化基金を設立し、個人的にも美術品収集に没頭し、富山の事務所には美術館を併設しました。これは、政府関係者や経済産業省幹部から「クールジャパン戦略」への協力を求められたことも動機の一つだったようです。
1992年、63歳の彦信氏は当時30代後半の長男俊太郎氏に事業を継承しました。しかし、約20年後に彦信氏が会長兼社長に復帰し、2017年には俊太郎氏が取締役を退任してイセ食品グループから離れ、事業承継は頓挫しました。同時期、農場建設への投資が100億円から150億円に膨張し、M&Aに起因するガバナンス悪化からグループ全体の信用が低下し、新規資金調達が困難になりました。代表者の頻繁な交代と経営幹部の相次ぐ辞任を招く彦信氏のワンマン経営も問題視されました。さらに、決算書に明記されない彦信氏個人へのグループ会社からの貸付という不適切な会計処理も行われていました。
2020年3月下旬、グループ各社が金融機関に返済猶予を要請し、私的整理手続きが開始されました。ただし、コロナ禍で業務用卵の売上は減少したものの、小売店で定価販売されるイセ食品の卵はコロナ禍での市況変動の影響を受けませんでした。主力の鶏卵販売は小売店での販売比率が高いため、売上の大幅な減少はありませんでした。むしろ、彦信氏個人への貸付や美術品購入といった本業以外への資金流出と、未熟な経営管理体制による信用失墜が主要な問題となっていました。
イセ食品グループは、彦信氏からの事業承継や美術品等の資産売却などの改善策について金融機関と合意しました。しかし、彦信氏の非協力的な姿勢により期限内に実現されず、資金調達はさらに困難となりました。2022年3月、株主である俊太郎氏と債権者である銀行により会社更生法の適用が申し立てられました。
彦信氏は令和の時代まで巨大な富を築いた実業家であり、高齢になっても精力的な人物でしたが、引退のタイミングを誤り、致命的な事業承継の遅れを招いてしまいました。
新興企業と老舗企業では倒産に至る要因は異なりますが、共通するのは経営者の判断力と適応力の重要性です。時代の変化を読み取り、適切なタイミングで重要な決断を下すことが、企業の存続に不可欠であることが、これらの事例から明らかになります。
全人類をデジタル管理 国際的な資本家(グローバリスト)がワクチンを推し進める理由はお金だけではありません。 今、国連は、SDGs(持続可能な開発目標)の「2030年までにすべての人に出生証明を含む法的なアイデン[…]
端末メーカーの経営破綻と給食事業者の突然死

大手スマートフォンメーカーの苦境ー富士通からFCNTへの変遷
NTTドコモの「iモード」対応第1号機を1999年にリリースしたのが富士通でした。その後同社は「らくらくホン」などシニア向けサービスの充実を図り、2010年代には「arrows」ブランドのスマートフォンを市場投入しました。しかし、アップル社のiPhoneの市場席巻により、国内携帯電話メーカーは事業撤退や統合を迫られることになります。
2018年1月、投資ファンドのポラリス・キャピタル・グループ株式会社が富士通から携帯端末の開発・製造部門を買収し、REINOWAホールディングス株式会社を設立、事業を分社化して傘下企業に移管しました。買収対象企業の資産や収益力を担保として金融機関から買収資金を調達するLBO(レバレッジド・バイアウト)スキームを活用し、少ない自己資金で効率的な事業展開を目指しましたが、スマートフォンの企画・開発・販売を担当したFCNTは収益確保に苦戦し続けました。
市場環境の変化と経営破綻
携帯端末市場の成熟化や買い替えサイクルの長期化により業績は著しく低迷し、円安と半導体不足による海外調達コスト増加も重なってグループ全体の資金繰りが悪化しました。2023年5月末、ついに民事再生法の適用を申請するに至りました。
法的整理手続き開始前にシニア向けSNSサービスなど一部事業はスポンサー支援を獲得できたものの、その他の事業についてはLenovo Group Limitedが支援意向を表明したのは民事再生法申請後でした。大手スマートフォンメーカーでさえスポンサー確保が困難な状況は、携帯端末業界での生存競争の激しさを如実に物語っています。
給食事業者の突然の事業停止による大混乱

ホーユーの事業拡大と成長戦略
1994年設立の株式会社ホーユーは、当初広島県内の学校給食や中国地方の官公庁・企業食堂運営を主力事業としていました。現社長が代表取締役に就任した2006年9月以降、提供先の学校や企業それぞれのニーズに応じて価格設定やメニュー構成を柔軟に調整し、契約先の拡大を推進しました。近年では岩手から鹿児島まで22営業所を展開し、全国規模での事業を展開していました。
コロナ禍による経営環境の激変
しかし2020年の新型コロナウイルス感染拡大により経営環境は一変しました。学校休校に伴う食堂運営休止、官公庁や企業での出社人数制限による食堂利用者の大幅減少により、業績は急激に悪化しました。コロナ禍の長期化によりオンライン授業や在宅勤務が定着したため、食堂利用者は回復せず、売上高は低水準にとどまり続けました。
突然の事業停止と混乱
2023年9月1日、多くの学校で夏休みが終わり新学期が始まるタイミングで、事前通知なしに一部食堂の運営が停止されるという事態が発生しました。ホーユー本社は休業告知もないまま閉鎖され、従業員には出勤不要との連絡があっただけでした。数日後に社長が記者会見を開き、食材価格・光熱費・人件費等の高騰が経営を圧迫し破綻に至った旨を説明しました。
構造的問題:過度な価格競争
しかし、コロナ禍や各種コスト上昇以前から、ホーユーの給食事業受託方式に根本的な問題がありました。公共施設の食堂運営は一般競争入札で決定されるため、同業者や大手企業との価格競争が激化しますが、ホーユーは極端に低い価格での落札を繰り返していました。
2022年度の帝国データバンクの調査によると、国内の企業・学生向け食堂運営・給食サービス事業者の34%が赤字経営で、前年度比で業績悪化した企業も6割を超えました。学校給食法の適用外である高校等への給食事業では、落札業者が予算内で食材調達から調理まで完結させる必要があります。食材価格や人件費上昇分の価格転嫁が困難なケースが多く、元々資金繰りが悪化していたホーユーでは不採算案件が増加していました。
利用者への深刻な影響と教訓
夏休み明けの突然の事業停止により、食堂や給食に依存していた学生たちは弁当持参を余儀なくされるなど大きな負担を強いられました。新規業者選定から食事提供再開まで相当な時間と費用を要します。
国内経済がインフレ局面にシフトしている現状では、価格転嫁が進まない企業の収益悪化は避けられません。他事業者と比較して極端に低価格を提示する業者については、契約期間満了まで適正な事業遂行が可能かを慎重に見極める必要があります。
両事例に共通するのは、外部環境の変化への適応力と財務基盤の重要性です。FCNTは技術革新の波に乗り遅れ、ホーユーは過度な価格競争により収益基盤を毀損しました。どちらも短期的な成果を優先し、長期的な持続可能性を軽視した結果といえるでしょう。
日本は、量的金融緩和のつけ、新冷戦、日本の財政赤字などの要因から、本格的なインフレ時代を迎えつつある。 現金の価値が相対的に上がっていたデフレ時代とは異なり、インフレ時代においては現金の価値は目減りしていく。よって資産運用[…]
書籍まとめ – 企業倒産事例集の価値と教訓
豊富な事例による包括的な学習機会
本要約では特に印象深い4社の事例を紹介しましたが、本書では計26社の多様な倒産事例が詳細に分析されています。業界、企業規模、事業ステージなど幅広い立場の企業を取り上げているため、読者は職業や立場を問わず、自身の業務環境に近い事例を見つけ出し、貴重な教訓として活用できるでしょう。
倒産の必然性とその理解
「なぜあの企業が倒産したのか」という世間の疑問の背後には、必ず倒産に至らざるを得なかった合理的な理由と経緯が存在することも理解できます。表面的には突然に見える企業破綻も、実際には複数の要因が重なり合った必然的な結果であることが明らかになります。
臨場感あふれるドキュメンタリー
巻末の最新レポートで取り上げられた船井電機の事例では、経営破綻の最終日の模様を記者が時系列で克明に描写しており、臨場感あふれる描写により読者はリアルな体験として受け止めることができます。この詳細な記録は、倒産という現実を抽象的な概念ではなく、具体的な出来事として理解させてくれます。
疑似体験の重要性
経営者であれ従業員であれ、倒産という事態はできる限り避けて通りたいものです。しかしながら、そうした望ましくない出来事だからこそ、多様な実例に触れて疑似体験を重ねることが重要なのではないでしょうか。
これらの事例は、将来の経営判断や職業選択において貴重な指針となり、同様のリスクを回避するための知恵として活用できるはずです。失敗から学ぶことの価値は計り知れません。他者の経験を通じて得られる教訓は、自らが同じ過ちを犯すリスクを大幅に減らしてくれるでしょう。
資本収益率(r)が経済成長率(g)よりも大きければ、富の集中が生じ、格差が拡大する。歴史的に見るとほぼ常にrはgより大きく、格差を縮小させる自然のメカニズムなどは存在しない。 20世紀に格差が縮小した原因は1914―1945年の世[…]