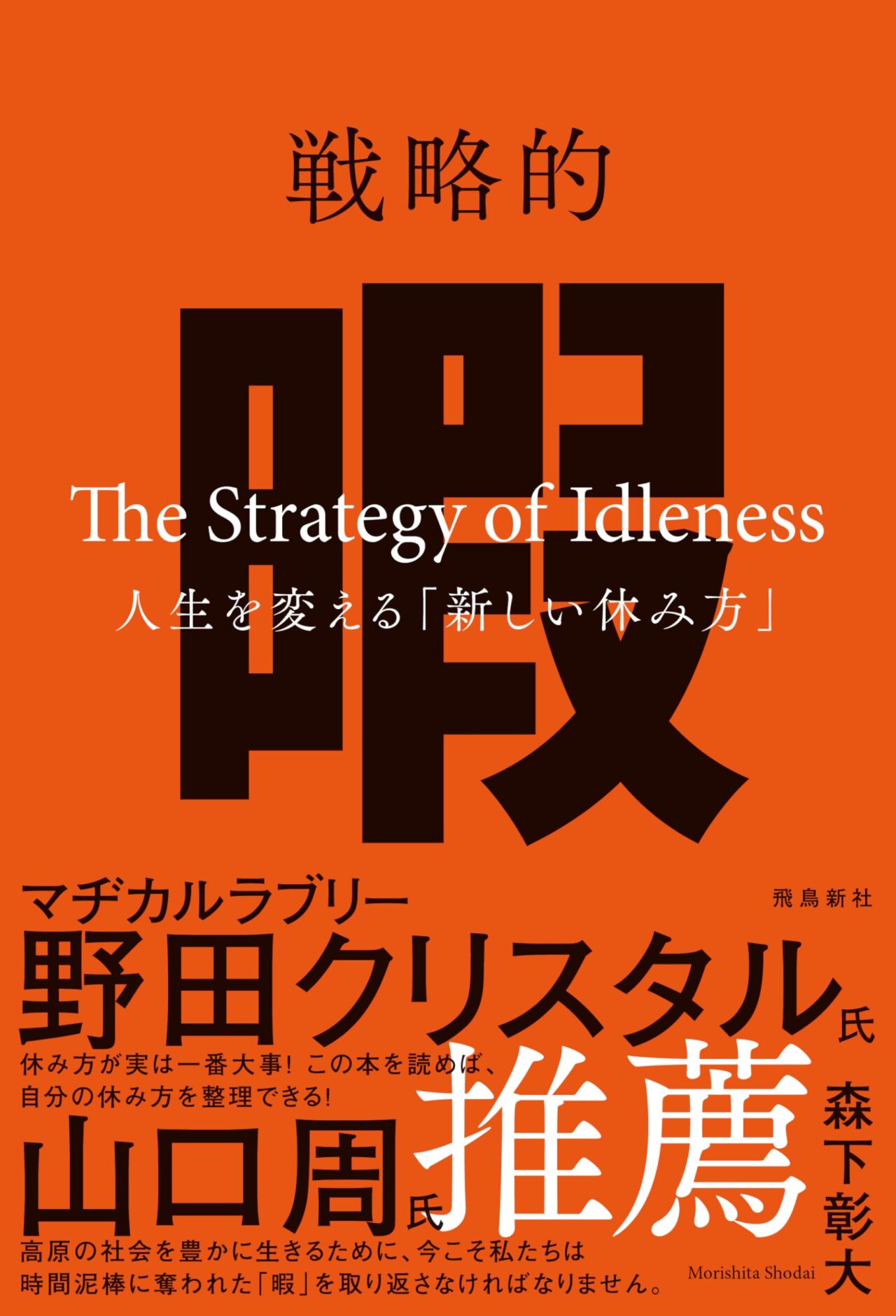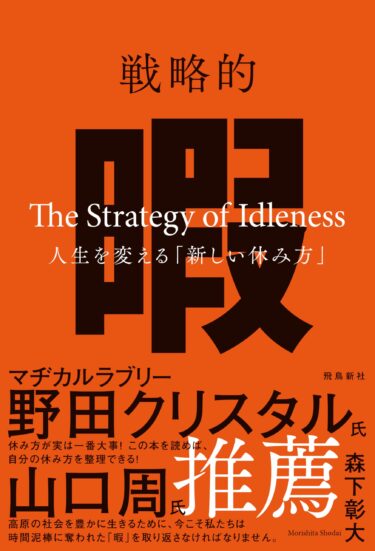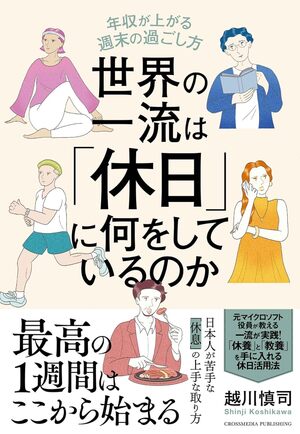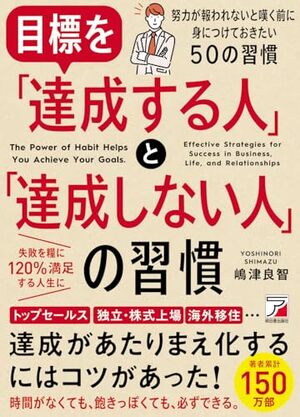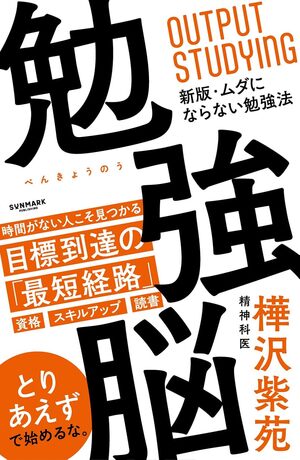- 私たちがデジタル技術と共にありつづけるためには、そのデメリットにも目配りしておく必要がある。
- 人間の注意力、集中力は「私たちの生活そのもの」である。しかし、テック企業はそれを「擬制商品」として売買している。
- テクノロジーは「満ち足りた余暇社会」を目的として設計・導入されなくてはならない。そのファーストステップがデジタルデトックスだ。
- 余暇の時間に、生身の人間として非効率を謳歌できることは、人生を彩り、愛おしくする。
デジタル時代が変えた私たちの心と体

集中できない現代人の実態
戦略的に「暇」を取り戻すには、まず現在のデジタル社会の実態を理解する必要がある。デジタル技術は確かに私たちに多くの利便性をもたらしたが、その恩恵を享受し続けるには、負の側面にも目を向けなければならない。
現代人のスクリーンタイムは年々増加しており、特に若い世代でその傾向は顕著だ。しかし本当に問題なのは利用時間の長さではなく、絶え間ない「ながら使用」だという。デジタル機器を断続的に使うことで、私たちの日常生活は細切れにされてしまう。アメリカの調査では、スマホユーザーは平均して5分ごとにスマホに手を伸ばしていることが明らかになった。こうして複数の無関係なタスクへ注意が分散され、脳は疲弊していく。スマホが視界に入るだけで、私たちの注意力は奪われるのだ。
スマホを外部記憶として頼り、注意が散漫になると、「いまここ」への意識が薄れ、上の空の状態が常態化する。その結果、自己のアイデンティティにも変化が生じかねない。短期記憶が長期記憶へと定着しにくくなり、創造活動に必要な材料が不足する。注意を向けられないことで、外部からの情報と五感を通じた内的な情報をつなぎ合わせることができなくなるのだ。
実は、創造的なアイデアは特定のタスクに集中している時ではなく、何も考えずにいる時に生まれる。この仕組みが「デフォルト・モード・ネットワーク(DMN)」だ。安静時に働くこの脳機能により、ぼんやりしている間に記憶や自我に関わる複数の脳領域が活性化し、互いに情報をやり取りする。DMN状態では脳内に蓄積された情報が整理され、それらが結びついてひらめきが生まれる。
スクリーンが体に与える影響
Microsoft社の元幹部リンダ・ストーンが行った非公式調査では、200人中8割がパソコンでメール確認中に呼吸が浅くなるか止まっていた。この現象は2023年の「ニューヨーク・タイムズ」紙で「スクリーン無呼吸」として報じられた。
動物は刺激に反応して身を守るため、呼吸のリズムを変化させる。狩りや逃走の際に発動するこの防御機能だが、現代人は似た種類のストレスに常時さらされている。スマホを開くたびに、予測不能な新しい情報が次々と飛び込んでくる。その結果、脳は常に興奮状態に置かれる。ストレートネックやスマホ腱鞘炎、手根管症候群などの症状が出ても使用をやめられないのは、この興奮状態が原因なのだ。
デジタル機器に長時間触れている子どもたちは、1981年と比べて外遊びの時間が半減しているというデータもある。運動は脳への血流を促進し、記憶を司る海馬の成長にも寄与する。体を動かさなければ前頭葉の機能が低下し、ストレス耐性が弱まって、スマホの誘惑に抗えなくなるという負のスパイラルに陥ってしまう。
細分化される「いま」
社会学者ハーバート・サイモンが提唱したアテンション・エコノミーは、情報過多の社会では注意力が希少資源となり、テック企業やメディアが人々の注意を奪い合う戦略を展開することを示した概念だ。現在、それは過度に人を引きつけるデザインとして具現化している。その結果、ユーザーのメンタルヘルスよりもプラットフォーム上での滞在時間が優先される事態が生じている。
私たちの注意力、集中力は「生そのもの」だ。しかしテック企業はそれを売買可能な「擬制商品」として扱っている。
社会心理学者ジョナサン・ハイトによれば、初期のソーシャルメディアは「アラブの春」や「オキュパイ・ムーブメント」といった民主的運動を促進したが、その後、人々のつながり、国家制度、共有される物語という社会の基盤を弱体化させたという。
「いいね!」などのシェア機能が実装され、「バズる」現象が誕生したことで、SNS企業は各ユーザーが反応しやすいコンテンツをアルゴリズムで表示するようになった。これによりSNSはバズを追求するゲームと化し、利用者は群集心理を強く意識した振る舞いを求められるようになった。感情を刺激するコンテンツで善悪が判断され、理性ではなく場の雰囲気によって、不適切な行為にも加担してしまう。誰もが「怒れる執行人」として「魔女狩り」に参加するようになったのだ。
ハイトは「ナウイズム」の問題も指摘する。ナウイズムとは、人類が長年積み重ねてきた知恵から人々が切り離され、古いものは時代遅れで、数値化できないものは無価値だと考える傾向を指す。そのため、自分の行動に対する即座のフィードバックを求めるようになる。
あらゆるものが高速化した現代では、深く没頭したり熟考したりすることが困難になり、歴史から切断された「いま」だけを生きることになる。電子メディアはこのナウイズムを加速させている。ハイトはこの現象がもたらす結果を次のように警告する。「過去についての確かな知識と、何世代もかけて洗練されてきた良いアイデアと悪いアイデアの選別がなければ、若者は周囲で流行するどんな劣悪なアイデアにも影響されやすくなる」と。
本書の要点 流たちの休日の過ごし方には、2つの共通点がある。「土日の休日を次の1週間を成功に導くための準備期間と考えていること」と「身体と心、脳のリフレッシュを図り、次の1週間に向けてエネルギーをチャージしていること」 世界[…]
新しい休み方:心を取り戻す2つのステップ
STEP1:デジタルとの関係を見直す

私たちが目指すべきは「満ち足りた余暇社会」である。大切な人との時間や、心から打ち込めることに没頭する時間を増やし、人生を豊かに生きる。テクノロジーはそのために活用されるべきであり、私たち自身も、そうした社会を能動的につくっていく必要がある。
では、どこから始めればいいのか。
デジタルデトックスの本質
最初のステップは、デジタルデトックス(DD)だ。ただし、ここでいうDDは、無理な我慢やスマホ断ちとは異なる。DDは問題そのものを解決するのではなく、解決に向けた心身のエネルギーを回復させる休養なのだ。一定期間、デジタル機器から離れ、現実世界での対話や自然とのつながりに意識を向ける。これがDDの核心である。
もはや「スマホは人の一部」となっており、単に「使う・使われる」という関係ではない。初めての場所でGPS付き地図アプリを開くとき、私たちは人間の身体だけでは不可能な認知と行動をしている。テクノロジーによって、自らの能力を拡張しているのだ。
私たちはすでにスマホやAIと「共にある」存在だ。問うべきは依存ではなく、共存のあり方である。
自立共生という視点
哲学者イヴァン・イリイチは、技術や生産性を追求するあまり、「自立性を失い、かえって害が生まれる状況」を「反生産性」として批判した。インターネットの普及とデジタル機器の高度化は、便利さへの強迫観念を強め、不要な情報が溢れて本当に必要な情報にたどり着けない状況を生んでいる。
この状況で重要なのが、イリイチの「コンヴィヴィアリティ(自立共生)」という概念だ。これは「自分が達成したい目的に応じて、道具を選ぶ自由」を意味する。コンヴィヴィアルな状態とは、デジタル技術と共生している状態のことだ。デジタル技術を使いこなせなければ、可能性を逃すことになる。一方で、依存しすぎれば、人間が支配され、自らのウェルビーイングを損なう。
著者が勧めるDDは、自分にとってのコンヴィヴィアルな状態、最適なバランスを探るためのものなのだ。
情報の質を高める
DDによって「デジタル上の有益な情報を逃してしまう」という懸念もあるだろう。しかし、誰かとの会話から得られる気づきや、自分の内なる直感こそ、見逃せない情報ではないか。デジタル上の情報は、多くの人に向けて最適化された均質的なものだ。平坦な道路や似たような建物に囲まれた都市に住むように、デジタル化された情報に浸り続けると、自然の持つ柔軟さや予測不可能性から遠ざかり、変化への対応力が弱くなっていく。
日本古来の「六根清浄」は、日常生活で乱れた感覚器官を自然の中で研ぎ澄ます試みだ。六根には五感に加え、意識(第六感)も含まれ、そのバランスを整えることで心身の理想的な状態に至るとされる。
現代人は情報過多により脳疲労を起こし、五感という感覚の定規が狂い、身体にも生活習慣病のような不調が現れている。DDは五感の働きを正常に戻し、想像力を高める。自然豊かな場所や美術館を訪れ、五感を喜ばせよう。
デジタルデトックスとは、スマートフォン、テレビ、コンピューター、タブレット、ソーシャルメディアサイトなどのテクノロジーデバイスの使用を控える期間を指します。デジタルデバイスからの「デトックス」すすは、気を散らすことなく実際の社会的相互作用[…]
STEP2:時間の捉え方を変える

時計時間の誕生
時計時間は、人間そのものを資源化するために重要な役割を果たしたテクノロジーのひとつだ。鉄道網の拡大により時刻の統一が求められ、1840年にイギリスのグレート・ウェスタン鉄道が標準時(GMT)を採用した。1880年には「時間の定義に関する法」が施行され、英国全土の標準時が法的に定められた。それまで自然のリズムとともにあった人々は、この標準時に合わせて生活のリズムを変えることを余儀なくされた。
時計時間は、労働管理や生産性、対価の算出を容易にした。時間に対する生産性を考えるということは、人間を一種の資源として捉えることでもある。この時計時間に縛られすぎず、自分の時間を測る物差しを、必要に応じて使い分けることが大切なのだ。
投じた時間に対する効果や満足度を「タイパ」と呼ぶ。時間は少ないほど良いという考えに基づき、可処分時間を増やすために時短や隙間時間の活用に取り組む。それ自体は悪くないが、執着しすぎると短期的な視点に陥る。直接話す手間を省いて誰かとつながれるSNSは、タイパを追求したものともいえる。しかし、オンラインのメッセージで意図が十分に伝わらなかったり、返信がなくて不安になったりして孤独感を抱くなら、それはタイパへの固執がもたらした弊害だろう。
時計時間を基盤とする資本主義社会では効率が絶対的な価値とされ、自由な時間や余暇にまで侵食している。登山も推し活も、楽しいからやっているのであって、コストや無駄がかかるかどうかは関係ない。余暇の時間に、生身の人間として非効率を謳歌できることは、人生を彩り、愛おしくするのである。
時計時間からの脱出
では、どうすれば時計時間から抜け出せるのか。ヒントは「フロー」と「不便」という2つの概念にある。
フローは心理学者ミハイ・チクセントミハイが提唱した概念で、「ゾーン」や「忘我」とも表現される。スポーツや音楽、学習、仕事などの活動に深く没入し、最大限の能力を発揮している状態を指す。その条件はいくつかあるが、ここで重要なのは「注意を逸らされない環境にいること」だ。DDの実践はここでも欠かせない。
もうひとつの「不便」とは、「不便から得られる価値」、いわゆる「不便益」の重要性である。この概念は京都先端科学大学の川上浩司氏が提唱した。便利であることは「早く結果が得られること」「労力がかからないこと」を求めるが、その時計時間的感覚に慣れすぎると、私たちが人生で味わうべきプロセスまで奪われてしまう。あえて不便にすることで、その瞬間だけの心動かされる体験を見出すのだ。
人生の質とは、その大量のプロセスを経てしか得られないものかもしれないのだから。
目標を達成する人は「必要か不要か」で判断するが、達成しない人は「好き嫌い」で判断する。 目標設定の際は、頑張れば達成できる「行動」を取り入れることが望ましい。 仕事は常に順調とは限らない。目標を達成する人は、最悪のケースも想[…]
まとめ
STEP2で時計という枠組みから自由になったあと、本書はSTEP3でさらに一歩踏み込む。「これこそが自分だ」という固定観念からの脱却である。肥大化した自我意識を手放し、ウェルビーイングを高める「スペース・パフォーマンス」の実践を提唱する。その考え方は、多くの読者が共感できる論理展開となっている。さらに巻末には、数分間で実践できるデジタルデトックスの具体的手法も収録されている。まずはスマホへの執着を少し緩めて、手軽な方法から試してみてはいかがだろうか。
コロナ禍のなか、テレワークやオンラインツアーにオンラインミーティング、オンラインセミナー、大学のオンライン授業、オンライン飲み会、そしてオンライン帰省などという意味不明なものもでてきて、何でもかんでもオンラインな世の中でう[…]