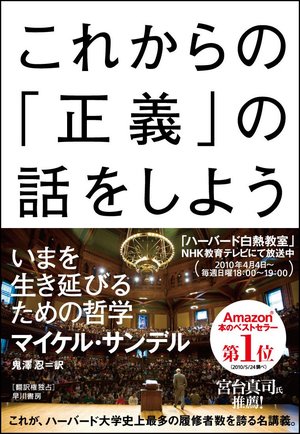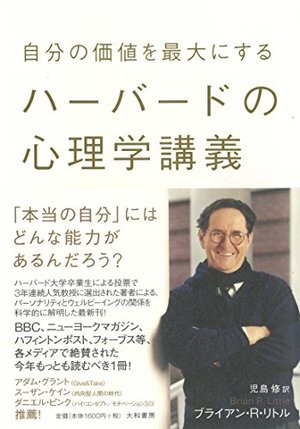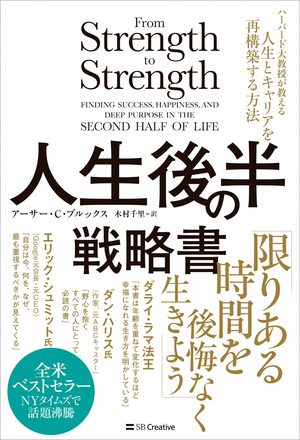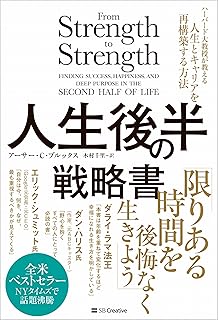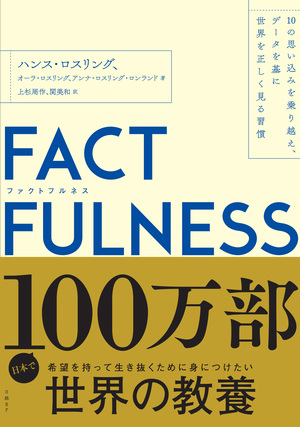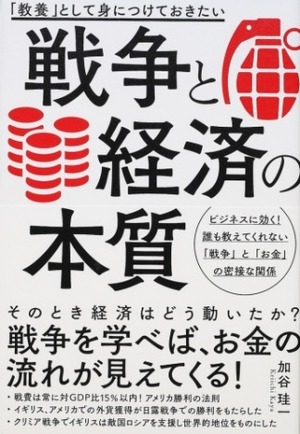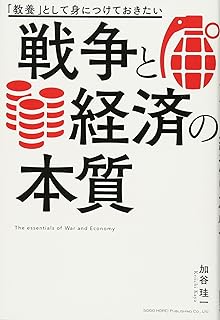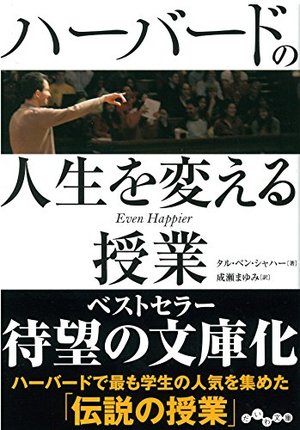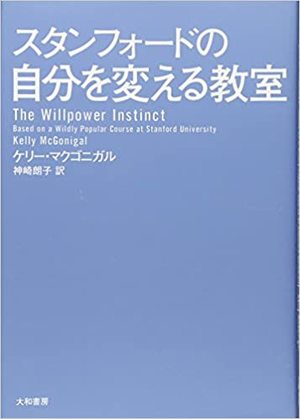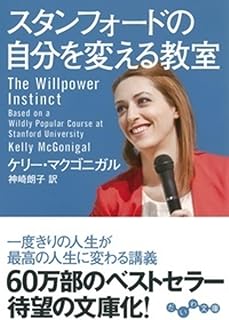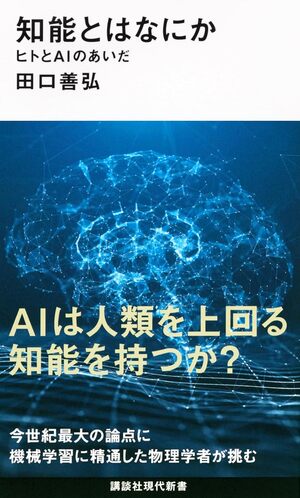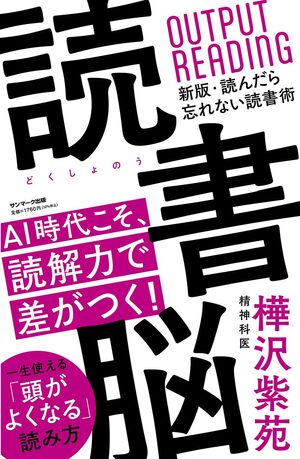- 正義の意味を探るアプローチには、①幸福の最大化、②自由の尊重、③美徳の促進、の三つの観点が存在する。
- 功利主義の道徳原理は幸福、すなわち苦痛に対する快楽の割合を最大化することである。この考え方の弱みは、満足の総和だけを気にしてしまうため、個人を踏みつけにしてしまう場合があることだ。
- リバタリアンが主張する自己所有権が認められれば、臓器売買や自殺幇助などの非道徳的行為もすべて容認されることになってしまう。
- われわれが自らの善について考えるには、自分のアイデンティティが結びついたコミュニティの善について考える必要がある。われわれは道徳的・宗教的信念を避けるのではなく、もっと直接的にそれらに注意を向けるべきだ。
正義を理解する三つの視点

災害時の価格問題から見える正義の本質
2004年夏、ハリケーン・チャーリーがフロリダを襲った後、被災地では生活必需品や修理サービスの価格が急騰した。この便乗値上げに対して、多くの住民が憤りを示した。
この現象をめぐり、異なる立場から三つの主張が展開された。
市場主義者の主張は、価格統制への反対である。彼らは、高価格によって供給業者の参入が促進され、結果として復興が加速すると論じる。この観点では、価格は個人の自由な決定に委ねられるべきであり、「公正な価格」という概念そのものが存在しないとする。
一方で、道徳的観点からの批判も存在する。この立場は、便乗値上げを単なる経済効率や個人の自由の問題として捉えるのではなく、本質的に非倫理的な行為として位置づける。
正義をめぐる根本的な問いかけ
この価格論争は、より大きな道徳的・法的ジレンマを浮き彫りにする。自然災害という他者の困窮に乗じて高額な対価を要求することは道徳的に許されるのか。売買当事者の契約自由を制限してでも、法的に便乗値上げを規制すべきなのか。
これらの疑問は、人間関係のあり方、法制度の設計、社会構造の理想像という、「正義」の核心に関わる問題を提起している。
正義への三つのアプローチ
正義を理解するための方法論として、便乗値上げ問題に見られた三つの視点が重要である。
第一に、幸福の最大化という功利主義的アプローチがある。これは社会全体の利益や満足度を最大化することを正義の基準とする考え方である。
第二に、自由の尊重という自由主義的アプローチが存在する。個人の選択権と自律性を最優先に置き、外部からの干渉を最小限に抑えることを重視する。
第三に、美徳の促進という徳倫理学的アプローチがある。道徳的品格や共同体の価値を重んじ、人間としてのあるべき姿を追求する立場である。
これらの理念は、それぞれ正義に対する独自の解釈を提供し、同時に固有の長所と限界を持っている。本書では、これら三つの思考枠組みを詳細に検討し、正義にまつわる諸問題への洞察を深めていく。
本書の要点 自分を知る パーソナル・プロジェクトから導かれる行動 あなたがレストランにいると、隣のテーブルには男性二人組が座っています。そのうちの一人が運ばれてきたステーキについて「焼き加減が良くない[…]
正義の探求:三つの哲学的アプローチ

最大幸福主義の光と影
功利主義の基本思想
ジェレミー・ベンサムが創始した功利主義は、道徳の根本原理を幸福の最大化に求める。この理論では、正しい行為とは快楽を増大させ苦痛を減少させるもの、つまり「効用」を最大化するものとされる。社会全体の幸福の総量を増やすことが、道徳的判断の基準となる。
個人の権利との衝突
しかし、功利主義には深刻な問題がある。全体の幸福を追求するあまり、個人の権利や尊厳を軽視してしまう危険性だ。
この問題を象徴的に示すのが、1884年に実際に起きたミニョネット号事件である。南大西洋で遭難したイギリス人船員4名のうち、3名が若い雑用係を殺害して食料とし、自らの命を救った。帰国後、3名は殺人罪で起訴されたが、彼らの行為は4名全員の死を防ぐための選択だった。
功利主義の論理に従えば、4名が死ぬより1名の犠牲で3名が生き残る方が「より良い結果」となる。だが、この結論は多くの人が感じる道徳的直感と衝突する。
中年期に入ると前頭前皮質の働きが低下する。この事実から逃れる術はなく、誰しもが中年期のキャリアの落ち込みに苦悩する。 人には「流動性知能」と「結晶性知能」の2つの知能が備わっているが、それぞれがピークを迎える時期は人によって異なる[…]
自由至上主義の理想と現実
リバタリアニズムの核心
リバタリアンは、個人の自由を最高の価値として掲げる。彼らの主張によれば、すべての人間は自由への基本的権利を持っており、この権利は経済効率や社会的利益よりも優先されるべきだ。
この立場から、彼らは以下を批判する:
- 安全のためのシートベルト着用義務などのパターナリズム
- 売春や同性愛を禁止する道徳的法律
- 富裕層への課税による所得再分配
自己所有権という理念
リバタリアンの思想の根底にあるのは「自己所有権」の概念だ。自分が自分自身を所有しているなら、自分の労働とその成果も所有している。したがって、政府が強制的に所得の一部を徴収することは、個人が政府に所有されていることを意味し、自由への侵害となる。
極端な結論への懸念
しかし、自己所有権を徹底すると、社会的に受け入れがたい結論に至る可能性がある:
- 臓器売買の完全自由化
- 医師による自殺幇助の無制限容認
- 合意に基づく食人行為の正当化
これらの帰結は、自由至上主義の理論的一貫性と社会的受容性の間の緊張を浮き彫りにする。
本書の要点 世界はどんどん物騒になり、社会の分断が進み、環境は悪化していると多くの人は思い込んでいる。しかし統計データを見ると、世界は基本的にどんどん良くなってきている。 人々が世界を誤って認識している原因は、本能からくる思[…]
自律と理性に基づく正義論
カントの自律的自由
イマヌエル・カントは、真の自由とは自律であると考えた。道徳法則に従うとき、私たちは偶発的な欲求や感情に支配されるのではなく、純粋な実践理性の主体として行動する。個人的利害や愛着から距離を置き、理性的判断に基づいて行為することが、人間の尊厳の源泉となる。
ロールズの無知のベール
ジョン・ロールズは、カントの自律概念を現代的な正義論に発展させた。彼の「無知のベール」という思考実験では、自分の社会的地位、能力、価値観などを知らない状態で、どのような正義の原理を選ぶかを問う。この仮想的な「原初状態」において、人々は公平で合理的な正義の原理に合意するだろうと論じた。
共通の課題:アイデンティティの軽視
カントとロールズの理論には重要な共通点がある。両者とも、道徳的行為者を個人的な目的や愛着から切り離された存在として捉えている点だ。
この抽象化により、彼らの理論は普遍的な道徳原理を構築できる一方で、個人のアイデンティティ、所属する共同体、歴史的・文化的背景といった、実際の人間存在を形作る要素を軽視してしまう危険性を孕んでいる。
これら三つのアプローチは、それぞれ正義の本質に迫る重要な洞察を提供するが、同時に固有の限界も持っている。現実の複雑な道徳的問題に取り組むには、これらの理論を批判的に検討し、統合的な視点を模索することが必要だろう。
国の経済力は戦争遂行能力に直結しており、戦争に勝つためには豊かで活発な消費経済の存在が不可欠である。 戦争や経済には、各国の関係性や地理的特徴が密接に結びついている。だからこそ、各国の政治指導者や軍関係者たちは熱心に地政学[…]
共同体への責任と忠誠のジレンマ

歴史的責任をめぐる問いかけ
現代社会において、私たちは先祖の行為に対してどこまで責任を負うべきなのだろうか。この問いは、ナチス・ドイツによるホロコースト、日本の従軍慰安婦問題、植民地支配など、歴史上の重大な過ちに対する公式謝罪をめぐる議論として具体化されている。
国家は過去の過ちを謝罪し、賠償を行うべきなのか。それとも、現在の世代は過去の行為に対して責任を負う必要はないのか。この問題は、個人の責任の範囲と共同体への帰属意識の本質に関わる深い哲学的課題を提起している。
個人主義的責任観の限界
自己責任論の論理
公式謝罪への反対論の根底には、明確な個人主義的責任観が存在する。この考え方では:
- 人間は自分自身の行為にのみ責任を負う
- 他人の行為や、自分の意志では制御できない出来事に対しては責任を持たない
- 過去の世代の行為に対して現在の世代が責任を負う理由はない
この論理は一見すると合理的で公正に思える。なぜ私たちが選択していない行為の結果を引き受けなければならないのか。
サンデルの批判:物語る存在としての人間
しかし、マイケル・サンデルは、こうした個人主義的な自由概念には根本的な欠陥があると指摘する。彼の主張によれば、人間は単なる個別的な選択主体ではなく、物語る存在として生きている。
私たちのアイデンティティは、個人の選択だけでなく、生まれ育った家族、所属するコミュニティ、歴史的・文化的背景によって形成される。この「位置ある自己」としての人間理解は、責任の範囲を根本的に拡張する。
共同体的責任の必然性
選択を超えた絆
私たちの人生を振り返ってみれば、選択とは無関係な理由で生じる責任や義務が数多く存在することが分かる:
家族の絆:両親や兄弟姉妹に対する責任は、私たちが選択したものではない。しかし、この絆なしには人間的な成長は考えられない。
地域への帰属:生まれ育った村や町、国への愛着や忠誠心は、理性的選択の結果というより、存在の根幹に関わる感情である。
歴史的継承:先祖の業績に誇りを感じ、同時に過ちに恥を感じることは、人間の自然な感情である。
仲間との連帯:困難な状況にある同胞への支援義務は、契約や合意を超えた道徳的要求として現れる。
意味ある人生の条件
サンデルは、こうした共同体的な絆や責任なしには、生きることも人生の意味を理解することも困難だと論じる。人間は孤立した個人として存在するのではなく、様々な関係性の網の目の中で意味を見出す存在なのだ。
政治における道徳的中立性の不可能性
リベラル派の試み
現代のリベラル派政治理論は、政治と法律を道徳的・宗教的な価値判断から切り離そうとしてきた。この試みの背景には、多様な価値観を持つ市民が平和的に共存するためには、国家が特定の道徳観や宗教観を押し付けるべきではないという考えがある。
中立性の不可能性
しかし、もし人間が本質的に共同体的存在であり、アイデンティティが特定のコミュニティの善と結びついているなら、完全な中立性を求めることは不可能であり、むしろ有害かもしれない。
現実の政治的争点を見れば、この限界は明確である:
- 正義と権利をめぐる議論の多くは、根本的には道徳的・宗教的問題と分離できない
- 堕胎、同性婚、安楽死などの問題は、技術的な政策論争を超えた価値観の対立を含む
- 社会保障制度や税制も、公正性や連帯に関する道徳的判断を前提とする
新たな政治的対話の必要性
これらの認識は、政治的対話のあり方を根本的に見直すことを要求する。道徳的・宗教的な価値観を政治から排除するのではなく、異なる価値観を持つ市民が建設的に対話し、共通の基盤を見出すための仕組みを構築することが重要になる。
結局のところ、私たちは選択した責任だけでなく、選択していない責任をも引き受けながら生きている。この現実を受け入れることで、より豊かで意味のある政治的・道徳的対話が可能になるのかもしれない。
要点 感謝の手紙を書くことは、人間関係からもたらされる意義と喜びをじっくり考察することだ。1通の手紙で幸福感は増す。 本当の幸福のため、不快な感情やつらい体験は必要だ。人は困難の克服により幸福になれる。困難こそが喜びへの感謝[…]
正義と共通善:政治における宗教の役割をめぐる転換

二つの対照的な演説
ケネディの分離主義:1960年
1960年、アメリカ初のカトリック系大統領を目指したジョン・F・ケネディは、プロテスタント系牧師会において歴史的な演説を行った。彼は明確に宣言した:「信仰は私的な事柄であり、公的責任とは何の関係もない」。
この演説は、単に反カトリック的偏見を和らげるための政治的戦略にとどまらなかった。ケネディの言葉は、リベラル派の中立性構想を体現していた。すなわち、政府は道徳的・宗教的問題に関して中立を保ち、個人が自由に自分なりの善良な生活の構想を選択できる社会を目指すという政治哲学である。
オバマの統合主義:2006年
それから46年後の2006年、バラク・オバマは大統領候補指名を控えた重要な時期に、ケネディとは真逆の内容の演説を行った。オバマは、宗教と政治論議の関連性を積極的に肯定し、信仰が公的な議論において果たすべき役割を強調した。
この劇的な変化は、単なる個人的な見解の相違を超えて、アメリカ政治における根本的な哲学的転換を示していた。
リベラル中立性の理論的背景
ロールズの哲学的擁護
ケネディの演説が表明した政治的中立性の理念は、1971年にジョン・ロールズによって『正義論』で哲学的に体系化された。ロールズは、**「政治的リベラリズム」**の核心として、以下を主張した:
- 現代社会では、善に関する包括的な教義について合理的な不一致が存在する
- 政治的制度は、特定の宗教的・道徳的価値観に依存すべきではない
- 公的理性による議論が、多元的社会における政治的合意の基盤となる
この理論は、宗教戦争の歴史を背景に、異なる価値観を持つ市民が平和的に共存するための政治的枠組みを提供しようとした。
保守派の反攻と中立性の限界
レーガン革命とキリスト教保守派の台頭
1980年のロナルド・レーガン大統領当選は、アメリカ政治における決定的な転換点となった。レーガン政権とともに台頭したキリスト教保守派は、以下の問題を政治的議題として前面に押し出した:
- ポルノグラフィーの法的規制
- 人工妊娠中絶の禁止
- 同性愛に関する法的制限
- 家族価値の政治的推進
リベラル派の戦略的困窮
共和党がこれらの道徳的・宗教的問題を積極的に政治化する中で、「政治には道徳的・宗教的判断が入るべきではない」と主張するリベラル派は、深刻な戦略的困窮に陥った。
中立性を掲げることで、彼らは以下の問題に直面した:
- 保守派の道徳的主張に対して実質的な反論ができない
- 市民の道徳的・精神的関心に応答する手段を失う
- 政治的議論から自ら撤退する結果を招く
この状況は、民主党にとって「雌伏の時代」をもたらした。政治的中立性を理想とする立場が、実際の政治闘争において不利に働くという皮肉な結果が生まれたのである。
オバマの新たな統合戦略
道徳的・精神的渇望への応答
2006年のオバマ演説は、このような政治的文脈の中で理解されるべきである。オバマは、アメリカ国内に広まる道徳的・精神的渇望に対して、リベラル派も積極的に応答すべきだと主張した。
彼の戦略は以下の要素を含んでいた:
- 宗教的価値観の政治的意義を認める
- 同時に、宗教的多様性を尊重する
- 道徳的議論を排除するのではなく包摂する
- 共通善への関心を政治的に表現する
中立性神話の克服
オバマのアプローチは、政治的中立性の不可能性を前提としていた。彼が認識していたのは、道徳的・宗教的議論に踏み込まないということは不可能だという現実である。
なぜなら:
- 政治的争点の多くは、根本的には道徳的価値判断を含んでいる
- 「中立性」それ自体も、一つの価値観に基づく選択である
- 市民の道徳的関心を無視することは、民主的正統性を損なう
新たな政治的対話の模索
共通善の復権
ケネディからオバマへの転換は、単なる政治的戦術の変化ではなく、共通善概念の復権を示している。この変化は以下を含意する:
- 政治は単なる利益調整ではなく、道徳的実践でもある
- 民主主義は、異なる価値観を持つ市民が共通の善を探求する過程である
- 宗教的・道徳的多様性は、排除すべき問題ではなく、豊かな対話の源泉である
残された課題
しかし、この転換は新たな課題も生み出している:
- 宗教的価値観を政治に取り入れながら、いかに宗教的少数派の権利を保護するか
- 道徳的議論を促進しながら、いかに寛容と相互尊重を維持するか
- 共通善を追求しながら、いかに個人の自由を確保するか
ケネディとオバマの対照的な演説は、現代民主主義が直面する根本的な緊張を浮き彫りにしている。完全な中立性も、一方的な価値観の押し付けも、多元的社会における政治的解決策とはならない。求められているのは、異なる価値観を持つ市民が建設的に対話し、共通の基盤を見出すための新たな政治的実践なのである。
意志力は、「やる力」「やらない力」とともに、「望む力」により構成される。それらは具体的な対策により強化できるものである。 意志力は、「食べ物」「住居環境」「エクササイズ」「呼吸」「睡眠時間」の調整により、高められる。 意志力[…]
共通善に基づく政治の新たな可能性

オバマの政治的転換とその意義
2008年大統領選挙において、バラク・オバマは道徳性と精神性を重視する政治を明確に打ち出した。この姿勢は、従来のリベラル派の中立性戦略からの大胆な転換を示していた。
しかし、選挙戦での修辞が実際の政治運営において共通善に基づく新たな政治へと発展するかどうかは、当時まだ不透明な状況にあった。重要なのは、この政治的転換が単なる戦術的変更にとどまらず、現代民主主義の根本的課題に対する新たなアプローチを示唆していたことである。
共通善政治の四つの柱
マイケル・サンデルは、共通善に基づく政治の具体的な内容として、以下の四つの要素を提示している。
1. 市民権、犠牲、奉仕:公民教育の復活
公正な社会の実現には、強固なコミュニティ意識が不可欠である。
現代社会では、個人の権利意識は高まっているが、全体への配慮や共通善への献身といった市民的美徳は衰退している。この状況を打開するためには、市民のうちに公共精神を育てる効果的な方法、すなわち公民教育の復活が必要となる。
具体的には:
- 公共サービスへの参加を通じた市民意識の醸成
- 個人の利益を超えた共同体への責任感の培養
- 民主的価値観と公民的美徳の教育
2. 市場の道徳的限界:価値の多様性の認識
市場は確かに生産的活動を調整する有用な道具である。しかし、すべての社会的価値を市場の論理で評価することには限界がある。
現代社会では市場原理が過度に拡張され、本来は市場の評価基準を適用すべきでない領域にまで浸透している。例えば:
- 兵役:軍事的義務を市場取引に委ねることの是非
- 出産・育児:代理母契約など生殖に関わる市場化
- 教育:学習成果に対する金銭的インセンティブ
- 環境保護:汚染権の売買システム
これらの領域では、効率性や経済的合理性だけでなく、道徳的価値や社会的意義を考慮した公的議論が必要である。
3. 不平等、連帯、市民道徳:公共領域の再生
極端な貧富の差は、民主的な市民生活そのものを脅かす。
経済格差が拡大すると、以下のような問題が生じる:
- 富裕層が公共サービス(公立学校、公共交通機関、公的医療など)を利用しなくなる
- 公共領域が空洞化し、異なる社会階層間の接触機会が減少する
- 共通の経験や関心事が失われ、連帯感とコミュニティ意識が衰退する
この悪循環を断ち切るためには、不平等が民主的な市民生活に与える公民的悪影響を正面から議論し、格差是正の方策を検討する必要がある。
4. 道徳に関与する政治:回避から対話へ
多元的社会において、道徳と宗教に関する市民の意見が一致することはない。しかし、だからといって政治がこれらの問題を回避することは不可能であり、有害でもある。
従来のリベラル派のアプローチは、道徳的・宗教的多様性に対処するため、政治的中立性を追求してきた。しかし、この戦略には根本的な限界がある:
- 完全な中立性は実際には不可能
- 回避の姿勢は市民の道徳的関心を無視することになる
- 結果として、政治への不信と反発を招く
相互尊重に基づく新たな政治的対話
回避から積極的関与へ
サンデルは、相互尊重に基づいた政治は可能だと論じる。そのためには、これまで以上に活発で積極的な市民生活が必要となる。
重要なのは、同胞の道徳的・宗教的信念を尊重するということを、それらを無視し、邪魔せず、関わらずにいることだと誤解してきた点である。しかし、このような回避の姿勢は:
- 相互理解の機会を奪う
- 偏見と不信を助長する
- 反発と反感を生み出す
直接的対話の重要性
代わりに、私たちは道徳的・宗教的信念を避けるのではなく、もっと直接的にそれらに注意を向けるべきである。これは以下を意味する:
- 異なる価値観を持つ市民との建設的な対話
- 道徳的議論を通じた相互理解の促進
- 共通の基盤を見つけるための継続的な努力
希望に満ちた政治の可能性
合意の保証なき対話
困難な道徳的問題についての公的議論が常に合意に至るとは限らない。しかし、対話を試みることなしには、合意の可能性を探ることすらできない。
重要なのは、結果の保証ではなく、対話のプロセスそのものが持つ価値である:
- 相互理解の深化
- 民主的な市民意識の醸成
- 公共的な議論文化の発展
公正な社会実現のための基盤
道徳に関与する政治は、単に回避する政治よりも希望に満ちた理想であるだけでなく、公正な社会の実現をより確実にする基盤でもある。
なぜなら:
- 市民の道徳的関心に応答することで、政治への信頼を回復できる
- 共通善への関心を通じて、社会的連帯を強化できる
- 多様な価値観を包摂することで、より包括的な正義を追求できる
共通善に基づく政治は、現代民主主義が直面する諸課題に対する野心的な解決策を提示している。その実現は容易ではないが、回避と中立性に依存する従来の政治よりも、はるかに豊かで意味のある民主的生活の可能性を秘めているのである。
スタンフォード大学ではオリンピックに優秀な選手を多く送り出してきた。そんなスタンフォード大学のノウハウをわかりやすく解説したのが本書である。 人にはドーパミン系とセロトニン系という2つの報酬システムが備わっている。これを意識的に切[…]