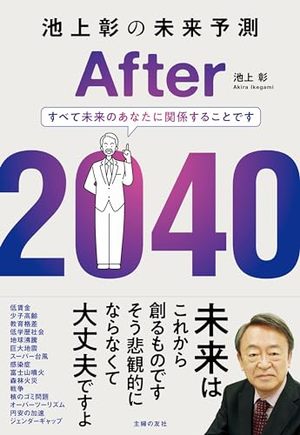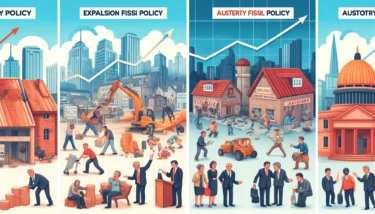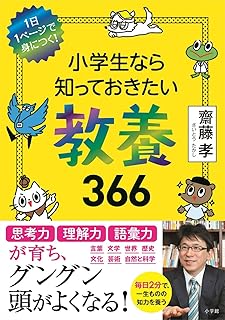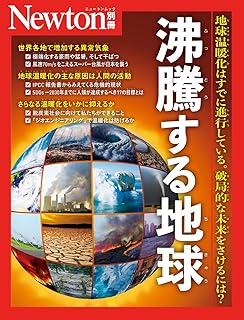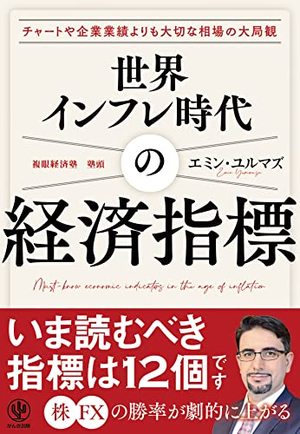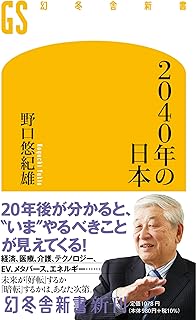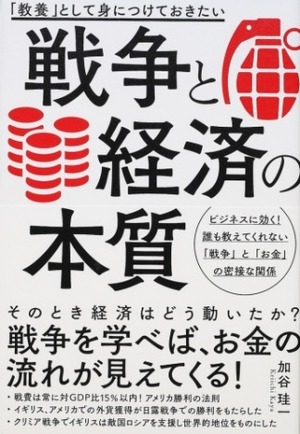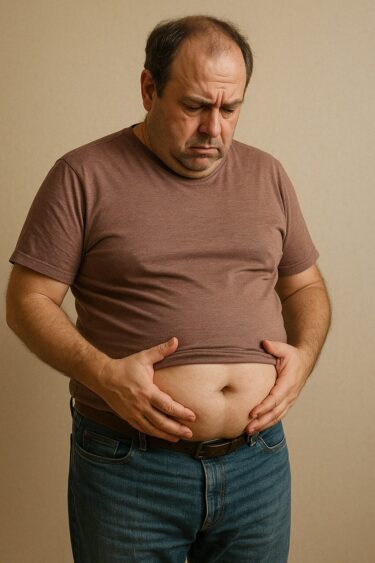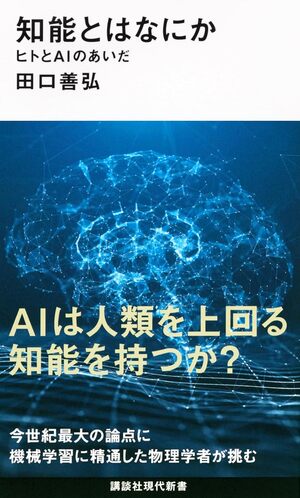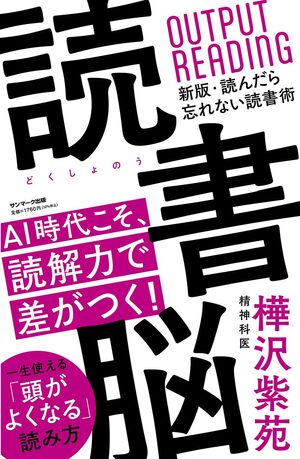- AIの進化により、多くの仕事が代替されていくだろう。しかし、過去にも消滅した仕事はたくさんあったが、それで失業率が上がっているわけではない。
- 子ども時代は視野を広げ、教養を身につけることが大切だ。教養はじわじわと効き、生涯にわたって役に立つ。
- 急激な円安の背景には、日米の金利差がある。ドル買い円売りが進むことで、日本円が海外に流れてしまうことが危惧される。
- 「ベーシックインカム」の導入に前向きな国はまだない。年金や健康保険などの社会保障を財源に充てるため、失敗したときのインパクトが大きいためだ。
仕事
AIは私たちの仕事を奪うのか?
生成AIの急速な進化に伴い、「将来自分の仕事が消滅するかもしれない」という不安を抱える人々が増えています。OpenAIとペンシルベニア大学の研究によれば、生成AIの普及はアメリカの労働者の約8割に影響を及ぼす可能性があります。参入障壁の高い弁護士などの専門職やホワイトカラーの職種も、分野によっては大きな変革を迎えるでしょう。
単純作業のアルバイトも減少傾向にあります。現在、ファミリーレストランではタッチパネル注文システムや配膳ロボットが人間に取って代わりつつあり、小売業界でもセルフレジを導入する店舗が急増しています。
しかし歴史を振り返ると、職業の消滅は新たな現象ではありません。かつて駅員は一枚一枚手作業で切符にハサミを入れていましたが、国鉄からJRへの民営化とともに自動改札機が導入されました。この変化で余剰となった駅員の中には、キヨスクの販売員へと職種転換した人々もいました。
その後JRは鉄道事業にとどまらない多角的経営へと発展し、新たな雇用も創出されています。一部の職業が消えても、必ずしも失業率が高止まりするわけではないのです。
長年従事してきた仕事が消滅するのは確かに寂しいことかもしれませんが、そのような変化の時こそ好奇心を持ち、新たな職業への挑戦を試みる絶好の機会と捉えるべきでしょう。
日本は「ものづくり幻想」から脱却せよ

日本は依然として高度経済成長期の「ものづくり幻想」から脱却できていません。現在では「世界の工場」中国が製造業で圧倒的な存在感を示し、品質も着実に向上しています。例えば電気自動車市場では、中国のEV最大手「BYD」が2022年に世界で約186万台を販売し、イーロン・マスク率いるテスラ(約131万台)を上回る実績を残しました。
日本の自動車メーカーがガソリン車にこだわり続ける間に、世界ではEV開発競争が激化しました。自動車産業の主流がEVへとシフトすると、日本のメーカーは単なる部品サプライヤーへと立場を変える可能性があります。AmazonやGoogleなどの巨大IT企業も自動運転技術の研究に参入しており、「テック企業が自動車産業を支配し、日本はハードウェア製造のみを担当する」という予測が現実味を帯びています。
「ソフト面」の状況も楽観できません。日本のマンガやアニメは世界的人気を誇ると言われますが、実際には日本のアニメ業界が中国の下請けになるケースも増えています。かつては安価な人件費を求めて中国にアニメ制作を委託していましたが、現在は逆に日本の方が安価なため、立場が逆転しているのです。
中国発のオリジナルアニメも国際的な人気を集めています。日本にも優れたクリエイターは存在しますが、単純に人口比で考えれば、中国には日本の10倍以上の才能あるクリエイターが存在する可能性があります。
日本は「ものづくり幻想」から脱却し、ソフト面やコンテンツ創造に一層の力を注ぐ必要があります。
財政政策は国の経済を管理する上で重要な手段です。積極財政と緊縮財政という二つの対照的なアプローチには、それぞれ独自の理論的根拠、期待される効果、そして実際の結果があります。本記事では、これら二つの財政政策の本質、主要国での実施例、そして特[…]
教育
オンライン教育が当たり前に
通信制高校の生徒数が急速に増加しています。2023年5月時点で、通信制高校に通う生徒は26万5000人に達し、全国の高校生全体の約9%を占めています。つまり、11人に1人が通信制で学んでいることになります。
通信制高校の特徴は、毎日決まった時間に登校する必要がなく、登校頻度も学校によって異なることです。学校への通学が苦手な生徒や、自分のペースで学習したい生徒たちが、この選択肢を選ぶようになっています。
この増加傾向の背景には、通信制高校自体の数の増加も影響しています。2021年には183校を数え、これは約20年間で4倍に増えたことになります。
注目を集めているのは、エンタメ企業KADOKAWAとその子会社であるIT企業ドワンゴが運営する「N高等学校」と「S高等学校」です。高卒資格取得と並行して自分の興味ある分野を学べる点が魅力となっており、選択制の課外授業ではプログラミングや音楽・ゲーム制作など、180以上のプログラムから選択できます。
コロナ禍を経てテレワークをする大人が増えたように、オンラインで学ぶ子どもたちの数も今後さらに増加していくと予想されます。
子どもには幅広い「教養」を

子どもたちが将来を考える際に「これほど多くの教科を学ぶ必要があるのか」「将来役立つスキルだけを身につけたい」と感じることがあるでしょう。
確かに、社会で働くにはスキルが必要です。しかし著者は「子ども時代に視野を広げ、教養を身につけることが非常に重要」だと主張しています。教養は徐々に効果を発揮し、一生涯活用できる財産となるからです。
例えば、寿司職人を目指す子どもが「早く一人前になりたいから学業は不要」と考えたとします。単においしい寿司を握るだけなら、それでも構いません。しかし「将来自分の店を持ちたい」という希望があるなら、経営の知識が必要になります。材料費の変動による利益率への影響、集客のためのマーケティング戦略、気候変動による水産資源の変化など、基本的な経済学や社会情勢の理解がなければ経営は難しいでしょう。
現代は学びの選択肢が豊富で、若いうちは寿司職人として技術を磨き、成人後に通信制高校や大学で学び直すことも可能です。大人も子どもも「教養」を軽視せず、学習機会を積極的に活用してほしいと著者は願っています。
自然災害
「地球沸騰」がもたらす気候変動
2023年7月、国連のアントニオ・グテーレス事務総長が「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰の時代が到来した」という衝撃的な発言をし、世界的な議論を呼び起こしました。「地球沸騰」という言葉からは全世界的な熱波を想像しがちですが、気候学者たちはむしろヨーロッパの寒冷化の可能性を警告しています。
ヨーロッパの主要都市は地理的には北海道よりも北に位置しながら、より温暖な気候を享受しています。この現象は「メキシコ湾流」と呼ばれる暖流によるもので、メキシコ湾から米国東海岸沿いに北極海へと流れ込み、パリやロンドンなどの都市に温暖な気候をもたらしています。
メキシコ湾流が北極海に接近すると海水が冷却され、真水部分が凍結します。すると塩分濃度が高まり比重が増した残りの海水は海底へ沈み込み、その空いたスペースに南からさらに暖かい海水が流れ込みます。この循環が地球の海洋システムを動かす重要な原動力となっています。
しかし「地球沸騰」によって北極海の氷が融解すると、メキシコ湾流の冷却・沈み込みプロセスが妨げられます。その結果、海流の循環が阻害され、南からの暖流がヨーロッパに到達しなくなり、皮肉にも寒冷化を引き起こす可能性があるのです。
このように、「地球沸騰」という気候変動は地域によって極端な高温や逆に寒冷化など、従来とは根本的に異なる気候パターンをもたらす恐れがあります。
脱炭素についての議論がますます活発化していますが、その裏には意外な事実が隠されています。本記事では、脱炭素ビジネスの実態や利権争いについて探っていきます。脱炭素ビジネスの怪しい実態とは環境問題への意識の高まりと共に、脱炭素ビジネスが急速に[…]
暮らし
円安・物価上昇が進んだ背景

日本は急速な円安に直面しています。2022年3月上旬には1ドル=115円程度だった為替レートが徐々に円安傾向となり、翌年春には1ドル150円台半ばまで下落しました。一時は160円台にまで達し、約34年ぶりの円安水準を記録しています。
この円安の主因は日米間の金利差です。日本が長期にわたりマイナス金利政策を維持する一方、アメリカは世界的なインフレを背景に2023年3月から政策金利の引き上げを開始しました。この金利差拡大により「資産は円よりもドルで保有したい」という心理が広がり、円売り・ドル買いの動きが加速したのです。
円安は輸出産業には追い風となりますが、輸入品価格の上昇を招きます。世界的な物価上昇はコロナ後の「リベンジ消費」やウクライナ情勢などの影響で2021年頃から進行していましたが、日本の場合は「円安」という固有の要因も重なりました。
日米の金利差がもたらす懸念材料は「日本円の海外流出」です。近年、日本国内でも外貨預金を選択する人が増加しています。円建て定期預金と比較してドル建て外貨預金の金利が魅力的なため、この傾向は自然な流れといえるでしょう。
しかし、多くの人がドル預金へとシフトすれば、さらなる円売り・ドル買いが進み、円安スパイラルを加速させるリスクがあります。円安に歯止めをかけるためには、10年以上継続してきた金融緩和政策の転換が必要だと著者は指摘しています。
「ベーシックインカム」は実現するのか?
「ベーシックインカム」とは国民全員に一定額を支給する制度で、働かなくても最低限の収入を保証するセーフティネットとしてコロナ禍で注目を集めました。
この制度には当然財源が必要です。そのため、年金や健康保険、生活保護などの既存の社会保障制度をすべて廃止し、その財源を国民全員に均等に分配するという考え方です。例えば一人7万円が支給されれば、5人家族なら35万円を受け取れますが、年金などはなくなります。また、就労は自由なので、働く人はその分だけ追加収入を得られます。
実現可能性についてはどうでしょうか。フィンランドでは失業手当受給者2000人を対象に実験が行われましたが、労働日数や収入額に変化はありませんでした。つまり「ベーシックインカムがあるから働かない」という人は増えなかったのです。
人間は生活に必要な最低限の収入があっても、「もっと豊かに暮らしたい」という欲求を持つものです。旅行や住宅購入などの目標があれば、これまで通り働くでしょう。
現状では、ベーシックインカム導入に積極的な国はほとんどありません。社会保障制度の根本的な改革が必要で、失敗した場合の社会的混乱が大きいためです。
日本でも限定地域での試験導入はあり得るかもしれません。もし突然「あなたの地域はベーシックインカムを導入します」と言われたら、あなたはどう感じるでしょうか。
日本は、量的金融緩和のつけ、新冷戦、日本の財政赤字などの要因から、本格的なインフレ時代を迎えつつある。 現金の価値が相対的に上がっていたデフレ時代とは異なり、インフレ時代においては現金の価値は目減りしていく。よって資産運用[…]
健康
医療現場のAI活用で病気を早期発見

医療テクノロジーの進歩により、疾患の早期発見・早期治療の可能性が飛躍的に高まっています。これに伴い、人間の平均寿命もさらに延伸することが予想されます。
現在、がんの診断にはCT(コンピューター断層撮影)やMRI(磁気共鳴画像診断)の画像が活用されています。放射線科医が画像から病変を特定する必要がありますが、経験豊富な医師でも見落としが生じることがあり、それが医療訴訟の原因となるケースも少なくありません。
しかし今後、AIがこの役割を担うことで、診断の見落としを大幅に減少させることが期待できます。すでに大量の医療画像データをAIに学習させるプロジェクトが始動しています。
さらに、診療現場へのAI導入により、経験の浅い医師でもAIの支援を受けながら最適な治療方針を決定できるようになるでしょう。多様な症例を学習したAIは、医師の専門外の疾患も早期に発見し、適切な診療科への紹介を可能にします。
食品添加物は私たちの健康に影響を与える可能性があります。この記事では、避けるべき危険な食品添加物について詳しく解説していきます。 食品を買い物する際に、ラベルを見ている方は多いかと思います。しかし、そのラベルにはわ[…]
まとめ
本書には数多くの「未来予測」が収録されているため、通読して全体像を把握されることをお勧めします。各章の結びには、著者による「明るい未来」と「暗い未来」のシナリオが要約されています。例えば「仕事」の章では、「明るい未来」としてAI導入による生産性向上、ワークライフバランスの改善、人手不足による賃金上昇などが描かれています。対照的に「暗い未来」では、深刻な人手不足による社会機能の低下、企業の革新力喪失、海外下請け化などが予測されています。
興味深いのは、「テクノロジーの進化」や「人手不足」といった同じ前提条件から、全く異なる未来像が導き出される点です。つまり、どちらの未来を実現するかは、現在を生きる私たち次第なのです。
本書の真価は、豊富なデータに基づきながら、池上氏ならではの明快な解説で理解を深められる点にあります。2040年は思いのほか早く訪れるでしょう。「明るい未来」を創造するためにも、ぜひ本書をご一読されてはいかがでしょうか。
国の経済力は戦争遂行能力に直結しており、戦争に勝つためには豊かで活発な消費経済の存在が不可欠である。 戦争や経済には、各国の関係性や地理的特徴が密接に結びついている。だからこそ、各国の政治指導者や軍関係者たちは熱心に地政学[…]