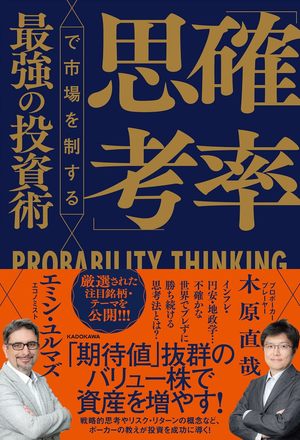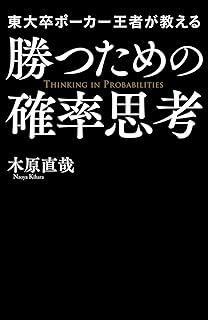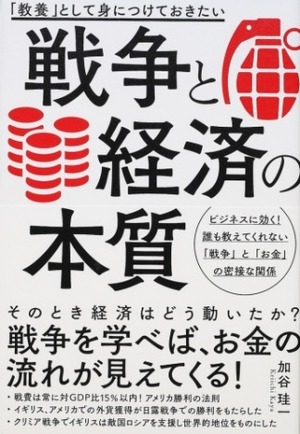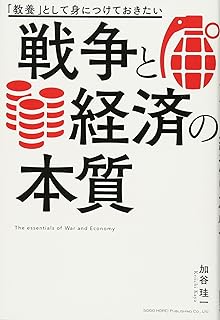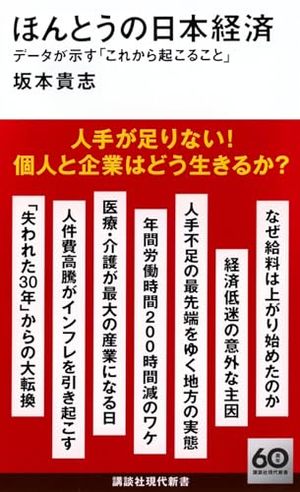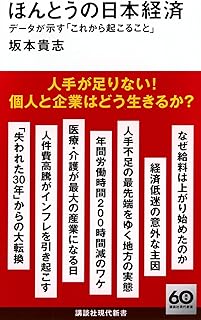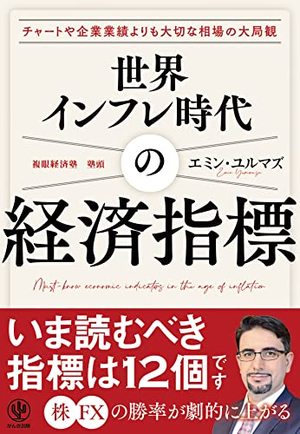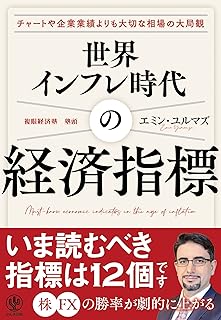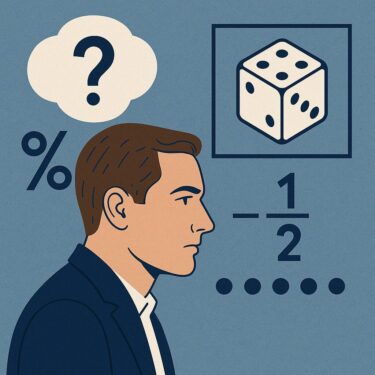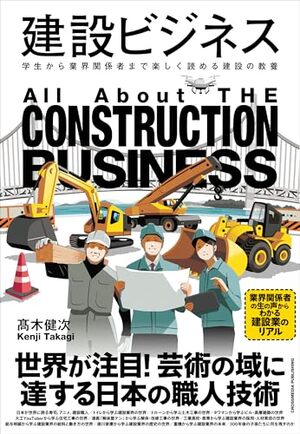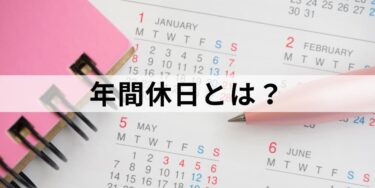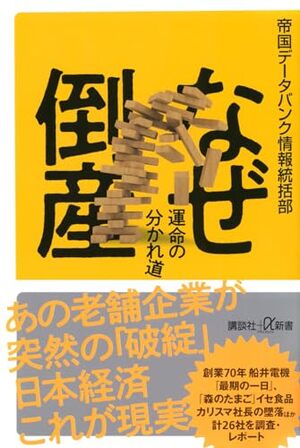- 個別株式投資とポーカーには多くの共通点がある。どちらもスキルと運の両方が必要で、リスク管理がものをいう。運がめぐってきたときにそれを活かせるかは、スキル次第だ。
- エミン氏は、市場成長の可能性や個別の企業のシェアを見極め、銘柄を選ぶ「ストーリー投資」を推奨している。木原氏が実践する投資法も、この一種である。
- インフレによって、日本株と経済は長期的に成長する可能性が高い。今後は投資をしていないことが大きなリスクになる。
投資とポーカーの共通点
ポーカーが強い人は投資も強い
木原氏:ポーカープロから株式投資へ成功の転身

日本を代表するポーカープレイヤー木原氏が本格的に株式投資を始めたのは約3年前のこと。2023年には株式投資の利益がポーカーでの収入を上回るまでになったという。
投資のきっかけは偶然だった。株主優待を目的に保有していた東京ドーム株が買収対象となり、その結果30万円ほどの利益を得たことが転機となった。この成功体験から積極的な投資へと方針を転換。当初の300万円の投資資金から、レバレッジを効かせる信用取引を活用し、現在では約1000万円規模の投資を行うようになった。
信用取引はハイリスクであるため初心者には向かないとのエミン氏の見解に対し、木原氏は「怖いという感覚は全然なかった」と述べる。ポーカーの世界では1回の勝負で200万円相当のチップを失うこともあるが、株式投資では投資額が一気にゼロになる事態は稀だからだ。
これを受けてエミン氏は、ポーカーと投資には多くの共通点があり、「ポーカーがうまい人は株式投資でも上達が早い」と分析する。実際、ポーカーのプロフェッショナルの中には株式投資で成功を収める人や、金融業界からポーカーに転身した人材も存在するという。
ポーカーと株式投資:実力とリスク管理の共通点

ポーカーは単なるカードゲームではなく、「カードを使ったベットゲーム、つまり『投資のゲーム』」としての本質を持つ。木原氏が指摘するように、ポーカーでは必ずしも強い人が勝利するとは限らない。将棋では初心者がプロに勝つことはほぼ不可能だが、ポーカーでは運に恵まれた初心者がトッププロを打ち負かすことも十分にあり得る現象だ。
エミン氏によれば、株式市場も同様の性質を持ち、特別な知識を持たない人が大きな利益を得ることもある。しかし両者に共通して言えるのは、純粋な運だけでは継続的な成功は望めないという点だ。もし運だけで成り立つなら、ポーカーで生計を立てる職業プレイヤーや専業投資家の存在自体が説明できない。
一時的な利益ではなく、長期的に好機を活かして利益を最大化していく能力は、明らかにスキルに依存している。さらに、不運な状況下でいかに損失を最小限に抑え、回復できるかという能力もまた、重要なスキルとなる。
リスクを取らなければ大きな勝利は得られないという点も、株式投資とポーカーの顕著な共通点だ。勝利したときの利益は、常に原資を失うリスクと表裏一体の関係にある。ハイリスク・ハイリターンの世界では、効果的なリスク管理能力が成功への鍵となる。
ポーカーと株式投資の現実:勝ち残るための真実
ポーカーの本質は「マイナスサムのゲーム」にある。参加者の99%が負け続け、プレイを重ねるほどチップが減少していく構造だ。素人がポーカーで負債を抱える最大の要因は「過剰な参加」にある。一方、株式市場では無償で取引を見送ることも可能だ。1992年から2006年の取引データ調査によれば、45万人ものデイトレーダーの中で利益を出せたのはわずか4000人に過ぎなかった。
木原氏は興味深い法則を指摘する。「実力が結果に与える影響は参加回数に比例するが、運の影響は参加回数の平方根に比例する」。この数理的特性により、多くの人々が自身の実力を見誤ってしまうのだ。
ポーカーでは、確率的に優位なプレイをしていても連敗することは珍しくない。同様に、株式市場でも投資家の技量や行動とは無関係に損失が発生することがあるとエミン氏は説明する。リーマンショックはその典型例だろう。
多くの共通点を持つ株とポーカー、どちらがより難しいのか。小遣い稼ぎ程度なら、ある程度の腕前を身につけてカジノでポーカーをする方が容易だが、生計を立てられるレベルを目指すと、対戦相手のレベルは飛躍的に上昇する。株式投資も継続的な収益確保は容易ではないが、生活できる程度の収入を得る難易度はポーカーより低いと木原氏は結論づける。
エミン氏も、億万長者を目指さない限り株式投資の方が難易度は低いと同意する。株式市場は取引量や規模が大きく、シンプルな投資戦略でも一定の成果を期待できるからだ。多くの人にとっての資産運用の理想的な目標は「人生にバッファ(余裕)を持つこと」であり、年5%の成長でも預貯金と比較すれば大きな資産形成が可能となる。「分散投資して放置するアプローチが、大多数の人にとっての最適解」なのだ。
国の経済力は戦争遂行能力に直結しており、戦争に勝つためには豊かで活発な消費経済の存在が不可欠である。 戦争や経済には、各国の関係性や地理的特徴が密接に結びついている。だからこそ、各国の政治指導者や軍関係者たちは熱心に地政学[…]
「確率思考」で制する最強の投資術
ストーリー投資と小型株戦略:個人投資家の強みを活かす

エミン氏が提唱する「ストーリー投資」は長期的視点に立った投資法だ。有望企業が属する市場の成長性と、その中での企業シェアに焦点を当てる。市場規模とシェアから算出される企業価値と比較して時価総額が割安であれば投資好機と判断し、市場成長に伴う時価総額の上昇が株価上昇をもたらす可能性が高いとする。
対する木原氏は機関投資家との直接競合を避け、「プロが注目しない小型株への投資」を戦略としている。大企業は複数の事業部門が株価にどう影響するか予測が難しい一方、事業構造がシンプルな小型企業は個人投資家でも分析しやすい利点がある。これもまた別形態の「ストーリー投資」と位置づけられる。
木原氏の投資判断には「最低二つの買い理由」という明確な基準がある。割安評価、連続増益、高い成長期待など複数の理由が投資継続の根拠となり、これらの理由が一つだけになった時点で即座に撤退するルールを徹底している。
「自分の納得できる基準や守りやすいルールを決めてシステマティックに売買する」という投資姿勢は重要だ。この規律があれば、保有理由を見失うことも、特定銘柄への過度の思い入れで合理的判断が鈍ることも避けられるだろう。
異なる投資アプローチと感情管理の技術
エミン氏の投資哲学は「魅力的な銘柄を発見したら即座に投資する」という即断即決の姿勢が特徴だ。彼によれば、最も重要なのは投資対象の真価を見極めることにある。時計の例を挙げるなら、本来100万円の価値があるロレックスが50万円で売られているとき、本物と確認できた時点で迷わず購入するほうが有利だと考える。
一方で木原氏は対照的なアプローチを取る。「衝動買い」を抑制するため、投資判断を1〜2週間熟考し、本当に必要な銘柄かどうか慎重に見極めることが多いという。
「勝算の薄いときは降りる」というポーカーの基本原則は、投資の世界でより難しい判断となる。ポーカーでは「テーブル上のチップは全額失っても構わない」という前提で利益最大化を図るが、株式投資では資金をゼロにはできない心理が働く。そのため木原氏は「ポーカー以上に厳しいリスク管理」の必要性を説く。「賭けた後に降りる」判断に慣れている木原氏にとって損切りは自然な行為だが、多くの投資家にとっては実行が難しい戦略だ。
一日で一般人の年収に相当する含み損が出ても冷静でいられる精神力は、ポーカープレイヤーならではの強みといえる。彼らは投資資金を単なる「お金」ではなく、ゲームのポイントのように捉える心理的距離感を持つ。ポーカーはこうしたメンタル面でも優れたトレーニングになるという。結局のところ「トレードには勝つ日もあれば負ける日もある」、それだけのことなのだ。
少子高齢化が進み人口減少経済に入った日本は、「人手を介したサービスへの需要」が高まる一方で、労働市場の需給がひっ迫し、深刻な人手不足に陥っている。 日本経済が低迷しているのは労働生産性の問題ではなく、労働投入量(総労働時間[…]
投資とポーカーに共通する心理的罠

投資家が陥りやすい認知バイアスの典型例として、成功しているポジションではリスク回避に走る一方、失敗しているポジションではむしろリスクを増大させるという矛盾した行動パターンがある。利益が出ている銘柄は理論的には買い増しが合理的なのに、多くの人は早期に利益確定してリスクを減らそうとする。反対に、損失を抱えた銘柄では損切りを避け、放置するかナンピン(値下がり時に同じ銘柄を買い増すこと)で対応してしまう。このような心理に支配され、借入金までして投資額を増やし、損失回復を図った結果、市場から退場を余儀なくされた投資家は少なくない。
この心理現象はポーカーの世界でも同様に観察される。大きく勝っているプレイヤーは過剰に慎重になりがちで、逆に負けているプレイヤーは冷静さを失い、博打的な一発逆転を狙ったプレイに走りやすい。本来は「負けている状況こそ、より慎重なプレイが求められる」のが正しい姿勢だ。
資産形成において重要な原則は「損切りは素早く、利益確定は遅らせる」という基本姿勢にある。この規律を守ることが、長期的な資産増加への鍵となる。
「確率思考」と『会社四季報』から導き出した注目銘柄
投資家の洞察:市場シグナルと投資戦略
木原氏は2024年5月下旬から7月中旬までラスベガスでポーカーのワールドシリーズに参加し、興味深い市場シグナルを察知した。S&P500やNYダウが史上最高値を更新していた時期にもかかわらず、カジノ内で景気の良い話題が皆無だったのだ。この異常な静けさから、「アメリカを主要マーケットとするセクターや銘柄への投資は控えるべき」との判断に至った。対照的に「日本に行った」「行く予定だ」「行きたい」という声は例年以上に頻繁に聞かれ、インバウンド拡大については確信に近い手応えを感じたという。
一方、エミン氏が『会社四季報』(24年3集夏号)から注目したのは、「鉄鋼」「金属製品」「その他製品」「輸送用機器」の各セクターだ。これらの選定は「セクター全体の増収率と増益率の分析」に基づいている。これらの指標が前期と比較して大幅改善している場合、株価も相応に上昇する傾向があるという。
PBR(株価純資産倍率)が1倍を下回る銘柄の最大の魅力は「下落リスクが極めて限定的」な点にある。将来的に株価上昇が見込めない可能性はあるものの、すでに下値余地がほとんどない水準まで割安になっているとも言える。配当利回りという形で「利息付き預金」のように保有できる利点もある。好転すれば大きな上昇余地が期待できるため、期待値は高いのだ。
日本は、量的金融緩和のつけ、新冷戦、日本の財政赤字などの要因から、本格的なインフレ時代を迎えつつある。 現金の価値が相対的に上がっていたデフレ時代とは異なり、インフレ時代においては現金の価値は目減りしていく。よって資産運用[…]
インフレを味方にできるか
インフレ時代の資産戦略と日本株の未来展望

インフレの本質は「貨幣価値の目減り」にあるが、それは同時に「実物資産や株式などの相対的価値上昇」を意味する。つまりインフレ環境下ではリスク資産価格が上昇する構造的特性がある。
エミン氏の母国トルコでは2020年以降、ハイパーインフレによって通貨トルコリラが暴落し、価値は約5分の1まで下落した。その結果、株価はインフレ率を大きく上回る10倍もの上昇を記録した。これは通貨暴落に危機感を抱いた国民が株式投資に殺到した結果である。
日本ではトルコほどの急激なインフレは想定しにくいものの、インフレ経済下では消費や投資が合理的な経済活動となる。実際、これまで投資に消極的だった層の市場参入が始まっており、新NISA制度という政策的支援が株式市場を一段と押し上げる可能性は高い。
「デフレ経済下で合理的だった預貯金」は、今後むしろハイリスクな選択となっていく。これは「下落局面にある日本円という単一銘柄への集中投資」に等しい状態だからだ。
現在の日本株上昇は主に外国人投資家によって牽引されている。流動性の高い先進国市場において、このような割安水準にあるのは日本株だけである。その背景には米中新冷戦に伴うグローバル資本の中国からの流出がある。その受け皿として日本が選択されつつある。有力海外企業の日本進出や投資は今後10年以上継続する見通しだ。短期的な調整局面はあるとしても、いずれ日経平均株価が「30万円に到達する日が訪れる」ことは確実だろう。
投資戦略の実践的洞察:プロの視点から学ぶ
本書では、両氏が注目する投資セクターの概略を紹介するにとどまらず、具体的な注目銘柄をリストアップし、個別企業名を挙げながらそれぞれの特徴や投資ポイントを詳細に解説している。投資に対する心構えや戦略はもちろん、推奨銘柄リストも実践的な参考資料として大いに価値があるだろう。
投資とポーカーの共通点という独自の視点から展開される投資戦略論は、一般投資家が陥りやすい失敗パターンを浮き彫りにする。十分なスキルを持たない状態での投資行動は、確率論的に見れば不合理な判断に陥ることが多い。
本書は投資初心者だけでなく、すでに市場で活動している中上級者にとっても、マインドセットを再考する貴重な機会を提供している。プロフェッショナルの思考法に触れることで、自身の投資判断を客観的に見直す契機になるだろう。