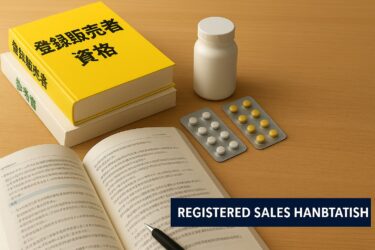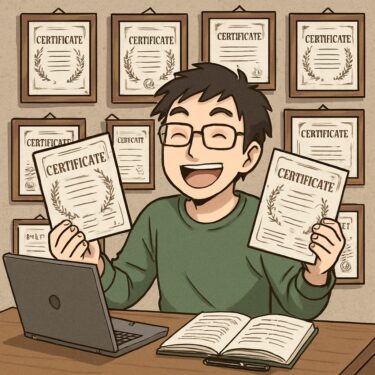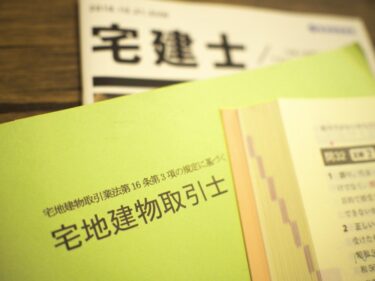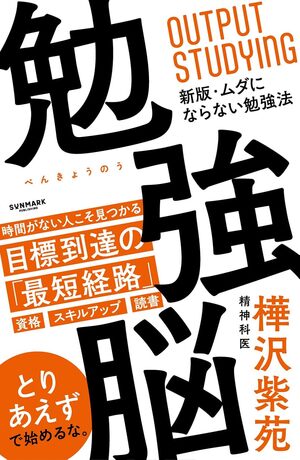行政書士とは
行政書士は、官公署に提出する書類の作成や提出手続きの代理、権利義務・事実証明に関する書類の作成などを行う国家資格者です。「街の法律家」として、市民や企業の身近な法的問題をサポートする重要な役割を担っています。
主な業務内容
- 許認可申請業務: 建設業許可、飲食店営業許可、風俗営業許可など約1万種類以上の許認可申請
- 権利義務に関する書類: 契約書、内容証明郵便、示談書、協議書など
- 事実証明に関する書類: 各種議事録、会計帳簿、実地調査に基づく図面類など
- 相談業務: 書類作成に関する相談
- 外国人在留資格関連: ビザ申請、帰化申請など
受験資格
行政書士試験の大きな特徴の一つが、受験資格に制限がないことです。
- 年齢、学歴、国籍を問わず誰でも受験可能
- 高校生や大学生でも受験できる
- 実務経験も不要
この点で、司法書士や税理士などの他の法律系資格と比べて、非常に門戸が広い資格といえます。
試験概要
受験料
10,400円(2024年度時点)
試験日程
- 試験日: 毎年11月第2日曜日
- 申込期間: 7月下旬〜8月下旬
- 合格発表: 翌年1月下旬
試験時間
13:00〜16:00(3時間)
合格基準
以下の3つの基準をすべて満たす必要があります。
- 法令等科目: 122点以上(244点満点中)
- 一般知識等科目: 24点以上(56点満点中)
- 総合得点: 180点以上(300点満点中)
合格率
例年**10〜15%**程度で推移しており、難関国家資格の一つです。
試験内容と科目別難易度
出題科目と配点
法令等科目(244点満点)
- 基礎法学: 8点
- 法の基礎理論、法制史など
- 難易度: ★★☆☆☆(範囲は広いが配点が少ないため深追い不要)
- 憲法: 28点
- 人権、統治機構など
- 難易度: ★★★☆☆(判例学習が中心で比較的学習しやすい)
- 行政法: 112点
- 行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、地方自治法など
- 難易度: ★★★★★(最重要科目で最も配点が高く、難易度も高い)
- 民法: 76点
- 総則、物権、債権、親族、相続
- 難易度: ★★★★☆(範囲が広く理解に時間がかかるが必須科目)
- 商法・会社法: 20点
- 会社法が中心
- 難易度: ★★★☆☆(出題範囲を絞って効率的に学習可能)
一般知識等科目(56点満点)
- 政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解
- 難易度: ★★★☆☆(足切りがあるため要注意。時事問題対策が必要)
出題形式
- 択一式: 5肢択一(46問)
- 多肢選択式: 3問
- 記述式: 3問(40字程度)
消防設備士資格の概要 消防設備士は、建物や施設の消防設備の設置、点検、整備を行う専門技術者の国家資格です。火災から人命と財産を守る重要な役割を担い、社会的意義の高い資格として位置づけられています。 消防設備士の資格は、業務範囲[…]
効果的な勉強法

必要な学習時間
- 法律初学者: 800〜1,000時間
- 法学部出身者: 500〜800時間
- 他の法律系資格保有者: 300〜500時間
学習スケジュール例(1年計画)
基礎期(1〜4ヶ月)
- 基本テキストを通読(1周目)
- 行政法と民法を中心に基礎固め
- 予備校の入門講座や動画講義の活用
充実期(5〜8ヶ月)
- テキストの2周目、3周目
- 過去問演習の開始(科目別)
- 判例学習の強化
- 一般知識の学習開始
直前期(9〜11ヶ月)
- 過去問の繰り返し(最低3周)
- 予想問題・模試の受験(3回以上)
- 弱点科目の集中補強
- 記述式対策の強化
科目別攻略法
行政法(最重要)
- 行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法の条文を徹底理解
- 判例は重要判例100選を中心に学習
- 過去問を最低5周は回す
- 地方自治法は頻出分野を重点的に
民法
- 債権法改正部分は特に重要
- 判例学習が鍵(判例百選活用)
- 条文と判例の関係性を理解
- 記述式対策として論理的な文章作成力を養う
憲法
- 人権分野の判例を徹底的に
- 統治機構は条文知識が中心
- コンパクトにまとめて繰り返し学習
一般知識
- 毎日ニュースをチェック(日本経済新聞、NHKニュースなど)
- 個人情報保護法、情報公開法は確実に得点
- 文章理解は国語力の問題なので過去問で慣れる
- 足切りがあるため侮れない
おすすめ教材
- 基本テキスト: 合格革命シリーズ、みんなが欲しかったシリーズ
- 過去問集: 合格革命 肢別過去問集
- 六法: ポケット六法または判例六法
- 予備校: LEC、TAC、伊藤塾、フォーサイトなど
学習のポイント
- 行政法と民法に全体の7割の時間を投入
- 過去問は最低3周、できれば5周
- 一般知識は毎日少しずつコツコツと
- 記述式対策は8月以降に本格化
- 模試は本番と同じ時間帯に受験
- 条文と判例の往復学習
資格の概要 第三種電気主任技術者(電験三種)は、電気事業法に基づく国家資格で、電気設備の保安監督業務を行うことができる資格です。電圧5万ボルト未満の電気工作物(出力5千キロワット以上の発電所を除く)の工事、維持及び運用に関する保安の[…]
資格取得のメリット
独立開業が可能
- 自宅や小規模オフィスでの開業が可能
- 初期投資が比較的少ない
- 定年がなく、生涯現役で働ける
業務範囲が広い
- 約1万種類以上の許認可申請業務
- 企業法務、相続、外国人在留資格など多様な分野
- 専門分野を持つことで差別化が可能
ダブルライセンスとの相性が良い
- 社会保険労務士との組み合わせ(企業の総合サポート)
- ファイナンシャルプランナーとの組み合わせ(相続・事業承継)
- 宅地建物取引士との組み合わせ(不動産業務)
キャリアアップに有利
- 企業の法務部、総務部での評価向上
- コンサルティング業務への展開
- 法律知識を活かした副業も可能
社会貢献
- 市民や中小企業の身近な相談相手
- 困っている人の問題解決をサポート
- やりがいのある仕事
社会保険労務士とは 社会保険労務士(社労士)は、労働・社会保険に関する法律の専門家として、企業の人事・労務管理をサポートする国家資格者です。労働基準法、社会保険法、労働保険法などの複雑な法律を熟知し、企業と労働者の橋渡し役として重要[…]
資格の需要と将来性
現在の需要状況
高需要分野
- 外国人在留資格関連: 外国人労働者の増加に伴い需要拡大
- 相続・遺言: 高齢化社会で相続案件が増加
- 建設業許可: 建設業界での継続的な需要
- 法人設立: 起業ブームによる会社設立サポート
- 補助金・助成金申請: コロナ以降、申請代行の需要増
登録者数
全国で約5万人の行政書士が登録(2024年時点)
将来性
プラス要因
- デジタル化への対応: 電子申請の普及で専門知識の需要増
- 国際化: 外国人在留資格業務の増加
- 高齢化社会: 成年後見、相続関連業務の増加
- 規制緩和: 新たな許認可業務の発生
課題要因
- AI・自動化: 定型的な書類作成業務の一部が自動化される可能性
- 競争激化: 登録者数の増加による競争
- 電子申請の普及: 個人でも申請しやすくなる
生き残るための戦略
- 専門分野の確立: ニッチな分野で専門家として認知される
- 付加価値の提供: 単なる書類作成でなく、コンサルティング機能を強化
- デジタルスキル: ITツールを活用した効率化と新サービス開発
- ネットワーク構築: 他士業や専門家との連携
- マーケティング力: ウェブサイト、SNSでの情報発信
1. 登録販売者とは 登録販売者は、薬事法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)に基づく医薬品販売の専門資格です。2009年の薬事法改正により新設された国家資格で、一般用医薬品(市販薬)の第2類・第3類医[…]
幅広い取り扱い業務
暮らしに役立つ相談
遺言・相続
遺言書の起案・作成の支援、遺産相続においては遺産分割協議書等の作成、相続財産の調査、相続人の確定調査など。
成年後見
認知症などにより判断能力が不十分な人を本人の自己決定権を尊重しつつ法律的に保護し支援するなどの成年後見人。高齢化社会に対応して、介護保険や成年後見の分野に携わることが出来ます。
自動車登録関連
自動車登録申請、自動車重量税申告、交通事故示談書、自賠責保険・任意保険金(後遺障害、損害賠償金)の請求。
契約書
交通事故に関する手続、土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等の契約書類の作成など。
土地活用
自分の畑に家を建てたい、畑を駐車場にしたい、農地を売りたいなどの、土地に関連する各種申請手続。
内容証明
債権債務問題に関する諸手続、内容証明郵便、公正証書等の書類の作成など。
日本国籍取得など国際関連
日本の国籍取得を希望する人の帰化申請の手続や、外国人登録、在留資格の取得、永住許可、国際結婚。
市民法務
内容証明書の作成、クーリングオフ、各種契約書、示談書、協議書。行政書士は「街の法律家」として、悪徳商法などの相談にも対応しています。行政書士会では市役所や駅構内などで「無料相談会」なども行っています。
ビジネスに役立つ相談
人関連手続
株式会社やNPO法人、医療法人、学校法人、宗教法人、組合等、法人の設立手続とその代理及び事業運営の支援(定款・議事録の作成、会計記帳、公的融資手続)など。会社設立の手続のみではなく、コンサルタントとして設立後に企業に対するサポートを行っている行政書士も沢山います。
知的財産権の保護
著作権登録、プログラム登録、著作権契約。これは比較的新しい分野です。
著作権の文化庁への登録申請は行政書士の専管業務。知的財産権の保護・啓蒙活動など。
外国人雇用関係
外国人を雇用する際に必要となる入国管理局への申請手続など。
中小企業支援
中小企業の経営を支援する外部専門家として、知的資産経営導入と知的資産経営報告書の作成・サポートなど。
運輸関連
一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業許可申請、タクシー営業許可申請など。
電子申請・電子調達
電子署名を要求される申請・届出、また電子申請手続の代理など。
許認可申請
建設業や運送業、産業廃棄物処理業、飲食店、化粧品の製造・輸入販売業等の許可申請手続など、様々な業種で許認可申請は必要不可欠です。
様々な許認可申請
建設業許可申請、入札資格申請、宅建業免許申請、風俗営業許可申請・営業開始届、飲食店営業許可申請、古物商・質屋等営業許可申請、深夜酒類提供飲食店営業開始届、旅行業登録申請、産業廃棄物処理業許可申請、農地法関連許可申請・届出
現代日本において、一つの興味深い現象が静かに広がっている。それは「資格マニア」と呼ばれる人々の存在である。彼らは資格取得そのものに強い情熱を注ぎ、時には実用性を度外視してでも次々と新しい資格に挑戦し続ける。この現象は単なる個人的な趣味を超[…]
資格の更新と維持費用
資格の更新
行政書士資格に更新制度はありません。 一度取得すれば生涯有効です。
登録手続き
初回登録時の費用
- 登録免許税: 30,000円
- 登録手数料: 25,000円(都道府県により異なる場合あり)
- 入会金: 200,000〜300,000円程度(都道府県行政書士会により異なる)
- 合計: 約255,000〜355,000円
必要書類
- 行政書士試験合格証書
- 履歴書
- 住民票
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 写真 など
年間維持費用
必須費用
- 会費(都道府県行政書士会)
- 年額: 60,000〜100,000円程度(地域により異なる)
- 日本行政書士会連合会費
- 年額: 約24,000円
- 合計: 年間約84,000〜124,000円
任意費用
- 研修費: 20,000〜50,000円/年
- 事務所維持費: 自宅開業なら0円、賃貸なら地域により異なる
- 保険料: 職業賠償責任保険など(任意)
- 広告宣伝費: ウェブサイト、名刺、チラシなど
継続教育(任意だが推奨)
- 研修制度: 各都道府県行政書士会が実施
- 専門分野別研修: 入管、許認可、相続など
- 倫理研修: 定期的に実施
- 新人研修: 登録後に受講が推奨される
注意: 研修受講は義務ではありませんが、実務能力向上のため積極的な参加が推奨されます。
資格概要 情報セキュリティマネジメント試験(SG:Security Management)は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する国家資格です。この試験は、情報セキュリティマネジメントの計画・運用・評価・[…]
まとめ
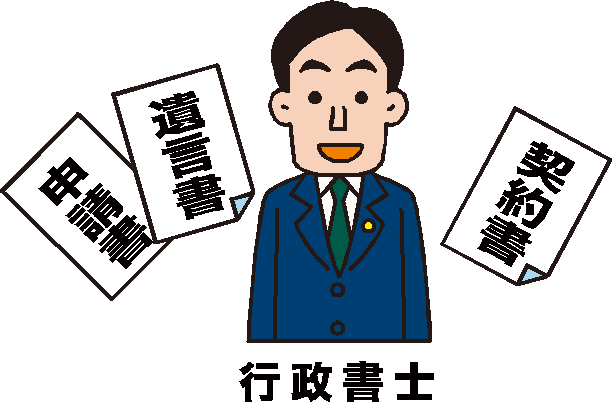
行政書士は、受験資格がなく誰でもチャレンジできる国家資格でありながら、取得後は独立開業も可能な魅力的な資格です。合格率は10〜15%と決して簡単ではありませんが、適切な学習計画と効率的な勉強法で合格を目指すことができます。
行政書士が向いている人
- 法律に興味がある
- 独立開業を目指している
- 人の相談に乗ることが好き
- 文書作成が得意
- コツコツと学習を続けられる
取得を決めたら
- 自分に合った学習スタイルを見つける(独学 or 予備校)
- 長期的な学習計画を立てる
- 行政法と民法を重点的に学習
- 過去問演習を徹底的に行う
- 一般知識の足切りに注意
資格取得後も継続的な学習と自己研鑽が必要ですが、その努力は必ず社会貢献とキャリアの充実につながります。ぜひ、挑戦してみてください。
宅建資格の概要 宅地建物取引士(通称:宅建士)は、不動産取引の専門家として法的に認められた国家資格です。2015年に「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」に名称変更され、より高い社会的地位と責任が求められるようになりました。 […]