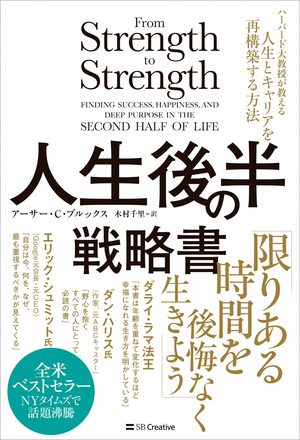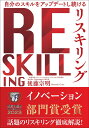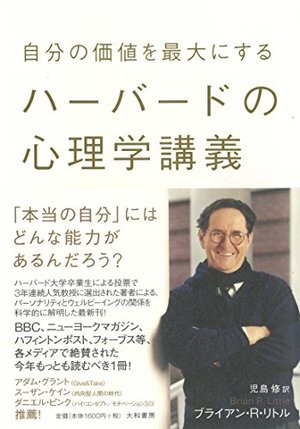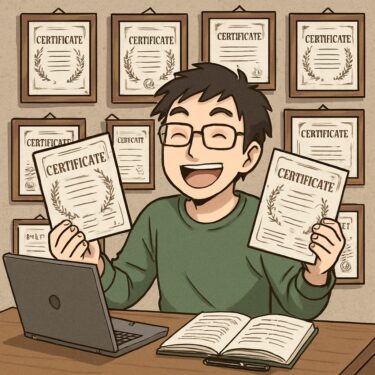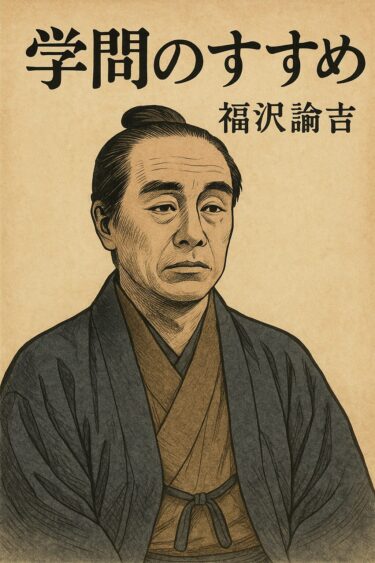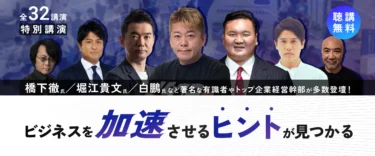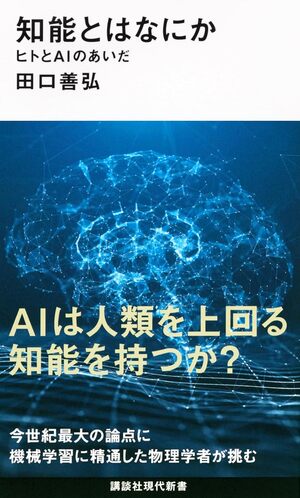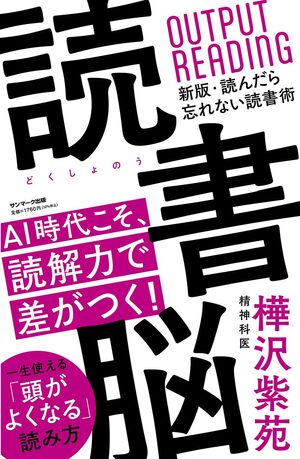本書の要点
- 40代でかつての第1志望であった早稲田大学に合格し、2度目の大学生活を送った著者は、「学び続ける」魅力にすっかりハマってしまった。
- 学びの究極の目的は、「自らを高めたい」という総合力的な要求である。もっといい人間になりたい、もっと知識のある人間になりたいという欲求に、学びはこたえてくれる。
- 大学に入り直したことによって、著者の仕事の幅が広がり、新たな学問分野への関心も高まっていった。
50代、人生3度目の大学生へ――「学び続ける」ことの価値

2度の大学生活を経験して
1991年、京都で生まれ育った私は18歳で法政大学文学部史学科に入学した。バブル経済崩壊後の重苦しい空気の中、浮足立つことなく4年間を過ごし、22歳で卒業を迎えた。
本命は早稲田大学だった。法政大学には心から感謝しているし、母校として深い愛着もある。しかし第7志望の大学にしか合格できなかったという事実は、長く心の奥に引っかかっていた。
卒業後は大学受験塾と東進ハイスクールで教鞭をとったが、30歳で両方を辞め、全国を転々とした後に結婚。40歳で受験サプリ(現スタディサプリ)の立ち上げに参画し、予備校講師と執筆活動で生計を立ててきた。
そんな中、ある疑問が膨らんでいった。第1志望に不合格のまま、受験業界で生徒を指導していいのだろうか――。この葛藤を乗り越えるべく、43歳で早稲田大学を再受験。2つの学部に合格し、2016年に教育学部で再び大学1年生となった。
40代の大学生活は予想以上に充実していた。試験での失敗やコロナ禍による混乱で留年も経験したが、6年かけて無事に卒業できた。
なぜ、また大学を目指すのか
仕事の実績だけでは満たされない「もっと学びたい」という欲求が湧き上がってきた。「数学や理科を学ばずに人生を終えるのはもったいない」――そう考えるようになり、今度は国立大学の理系学部を目指している。「大学院に進めばいいのでは」という声もあるが、それは次の段階で考えたい。50代、60代、70代と、新しい分野を学び続け、そこから世界に挑戦していくつもりだ。
もちろん、言うのは簡単だが実行は難しい。2025年にも国立理系大学を受験したが、英語、数学、そして新設された情報科目に苦戦し、ほとんど勘でマークシートを埋めるという散々な結果に終わった。
それでも大学や大学院に通い続けたいと思うのは、2度目の大学生活で「学び続けることの魅力」に目覚めたからだ。確かに学びには苦しさも伴う。しかし、「それを上回る価値がある」と実感している。より多くの人に、生涯学び続けることの魅力を知ってほしい。
中年期に入ると前頭前皮質の働きが低下する。この事実から逃れる術はなく、誰しもが中年期のキャリアの落ち込みに苦悩する。 人には「流動性知能」と「結晶性知能」の2つの知能が備わっているが、それぞれがピークを迎える時期は人によって異なる[…]
学び続ける意味とは
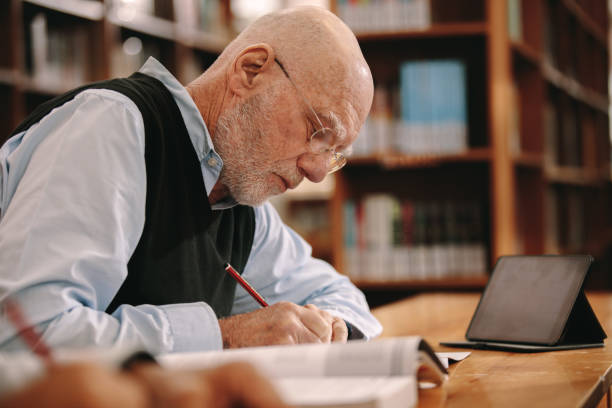
目的なき学びの価値
学び直しを考える人の中には、「仕事のスキルアップ」「専門性の向上」といった明確な目的を持つ人もいるだろう。しかし私は、学びに具体的な目的がなくてもいいと考えている。「自分を高めたい」という総合的な向上心こそが、学びの根本的な動機となる。「より良い人間になりたい、より豊かな知識を持ちたい」――その欲求に応えるのが学びなのだ。
法政大学時代の私は、学問そのものよりも就職準備に時間を費やしていた。学士号は取得したものの、何かを深く学んだという実感はなかった。大学時代に「学び」が不足していたことを痛感したのは、予備校講師や物書きとして一定の実績を積んだ後のことだ。様々な職業経験を通じて、「自分が知らないことがいかに多いか」を思い知らされた。それなのに「先生」と呼ばれている――この違和感が、職業経験を「学び続ける」という営みへと昇華させなければならないという衝動を生んだ。
「学び」は特別なことではなく、「シンプルに面白い」。そのことに気づいたのが、人生に少し余裕が出てきた43歳のときだった。
予測不能な時代だからこそ
現代社会は「VUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)の時代」と呼ばれる予測不能な時代だ。「デジタル化のスピードについていけない」と感じる人も多く、デジタルディバイド(情報格差)は深刻な課題となっている。
世界でも日本でも、想定外の出来事が次々と起きている。こうした時代だからこそ、「広く浅く学びたい」と思うのだ。
私が大学という高等教育機関にこだわる理由はいくつかある。まず、高校までの学習内容は良質な教材が充実し、独学も十分可能になってきた。一方、大学で学ぶ内容はそれほど敷居が高くないにもかかわらず、講義を担当するのは博士号を持つ専門研究者という安心感がある。少なくとも私にとって、大学で得られるものは大きい。年齢や環境を考慮したとき、タイムパフォーマンスやコストパフォーマンスが最適かはわからないが、決して悪い選択ではないはずだ。
本書の要点 自分を知る パーソナル・プロジェクトから導かれる行動 あなたがレストランにいると、隣のテーブルには男性二人組が座っています。そのうちの一人が運ばれてきたステーキについて「焼き加減が良くない[…]
学び続けて得られたもの・気づいたこと
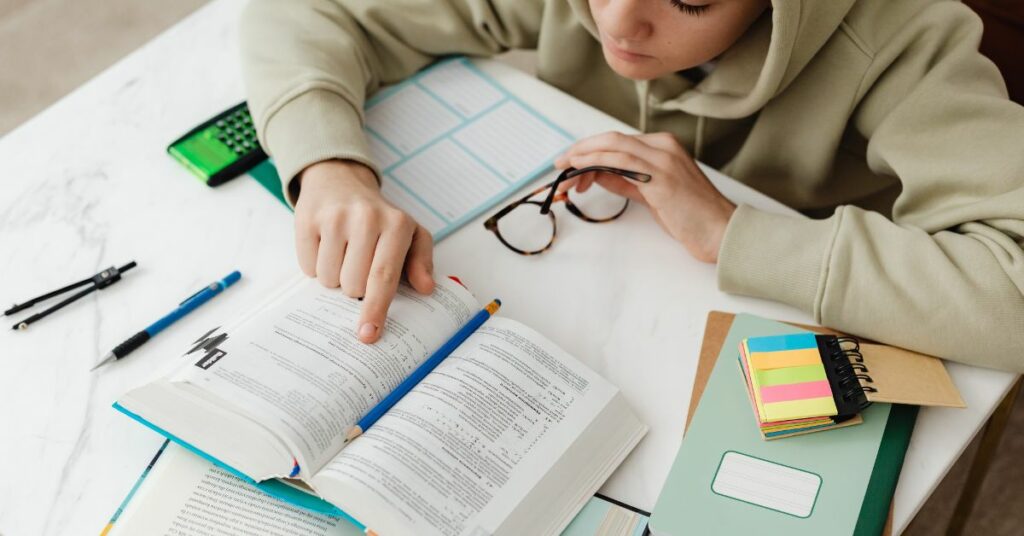
私生活における恩恵
学び続けることで私生活にもたらされた最大の恩恵は、人脈の広がりである。大学で出会った教員や同級生との関係は、卒業後も続くケースが少なくない。著者にとっては、ゼミの指導教員である小林敦子先生との出会いが特に大きな意味を持った。「現場主義」を掲げるゼミでの活動を通じて、年齢や立場を超えて人と関わる積極性が身についた。ゼミの研修地である広島県大崎上島町では「地域活性化プロジェクト」の関係者とのつながりが生まれ、以来、この魅力あふれる瀬戸内の島を毎年訪れるようになった。
2つ目の恩恵は、「一定の学力を持つ20代前後の若者の流行や価値観に触れられること」である。25歳ほど年下の学生と日常的に接することで、言葉の使い方ひとつとっても、さまざまな刺激を受けることになった。
3つ目の恩恵は、他者からの見え方や相手の感情への配慮が増したことだ。大学という場において、社会人学生はマイノリティである。少なくとも周囲に不快感を与えないよう、服装や身だしなみにも意識を向けるようになった。
これと関連して、自分の年齢を素直に受け入れられるようになったことも大きい。社会人学生の中には「失われた青春の回復」を求める人もいるが、純粋に「学ぶこと」に集中したほうが実りは大きいだろう。若い世代から温かく迎えられても、同世代として扱われることはない。むしろ、若者とは異なる役割や振る舞いを果たすべきだという認識を持つようになった。
4つ目の恩恵は、「多様な『学び』への関心が広がったこと」である。受験準備のため、長年避けてきた英語と国語を基礎から学び直したところ、かつての躓きポイントが明確になった。語学や古典の面白さを再発見し、TOEICへの挑戦や百人一首・漢詩の読書といった新たな行動につながった。教育学部では文系理系を問わず豊富な教養科目を履修でき、多方面から大きな刺激を得られた。
仕事における恩恵
仕事面での最大の恩恵は、活動領域が拡大したことだ。入学からしばらく経った頃、学内のWEBメディアにインタビュー記事を掲載してもらう機会に恵まれた。それを目にした編集者から声がかかり、初めての新書執筆へとつながった。これを契機に、別の企画提案も採用され、執筆活動の幅が広がっていった。また、学内で知り合った社会人学生がラジオプロデューサーだったことから、調布FMで『伊藤賀一のPM11』という番組を担当することになった。「早稲田に通っていなければ、決して実現しなかった展開」である。
2つ目の恩恵は、「仕事の現場で有効な話題提供ができること」だ。大学に再び通っていることを話すと、ほぼ例外なく好意的な反応が得られる。若者の動向に詳しくなったのと同様に、仕事に活かせるヒントが至るところに存在していた。
通学のために、午前から夕方にかけての仕事を削らざるを得ない葛藤はあったが、結果として大学での新しい出会いが仕事の機会を増やしてくれた。
学び続けることの課題
私生活における課題は、家族と過ごす時間が減少したことだ。妻は正社員として働き、自分は仕事を減らして「学び直し」に取り組むという状況下で、受験勉強中の秋に娘が、2年生の秋に息子が誕生した。育児では駅前の保育施設や近隣に住む妻の両親に多くを頼ることになった。このような問題は、独身者や子どものいない共働き夫婦なら生じにくいと考えられるが、仕事との兼ね合いが多くの人にとって最大の課題となる点は変わらない。
学生生活と仕事・家庭の両立は、時間的にも体力的にも相当な負担がある。大学での「学び直し」は、明確な目的意識と、家族の理解、そして体力面での自信がなければ、実現は困難である。そうした条件が整わない場合は、カルチャースクールや大学の公開講座などを選択するのも一つの方法だ。
仕事面での課題は、「短期的な収入減少」である。学費や交通費が発生し、物理的に時間が奪われるため、手元の資金は確実に減っていく。ただし、著者のように再入学が結果的に収入増加につながる可能性もある。「学び直し」を機会として捉え、職業人としての転換を図ることもできるだろう。
学習態度の形成:その起源 学習への姿勢は、幼少期から徐々に形成される複雑な心理的メカニズムの結果です。同じ家族、同じ学校環境で育っても、人によって学びへのアプローチは大きく異なります。 初期体験の重要性 […]
社会人の学び直しを成功させるために

限られた時間を有効活用する方法
社会人が大学で学び直しをする際、時間不足に悩まされるのは避けられない。その要因は人それぞれだが、確かに経済的余裕があれば解決できる部分は大きい。しかし、誰もが金銭的に恵まれているわけではない。そこで、お金をかけずに実践できる時間活用術を紹介したい。
通学時間を物理的に短縮するには引っ越しが有効だが、費用面で現実的ではないことも多い。そこで重要になるのが「意識の転換」だ。通学時間を「集中して音声学習ができる貴重な時間」と捉えたり、「健康維持のためのウォーキング時間」として前向きに活用したりすることで、移動時間の価値を高められる。
また、大学での過ごし方も工夫が必要だ。単位取得が極端に困難な科目ばかりを選ぶと、挫折のリスクが高まる。興味のある重要科目には真剣に取り組みつつ、比較的単位を取りやすい科目も適度に組み合わせるバランス感覚が大切だ。単位を落として留年すれば、時間もお金も無駄になってしまう。「学び続ける」という長期的視点に立てば、心身ともに無理をしすぎないことが何より重要である。
学び続けるための3つの心構え
継続的な学びを実現するには、次の3つの姿勢が欠かせない。
第一に、学びを実践の場と結びつけることだ。例えば、幅広い年齢層に歴史や社会科を教える立場にあったからこそ、生涯教育学を学ぶ必然性が生まれる。現在の自分に不足している知識やスキルを見極め、既に持っている経験や知識と組み合わせながら、次の学習テーマを選んでいこう。
第二に、学び続けている人々とのつながりを持つことだ。そうした人々との交流は大きな刺激となり、モチベーションの源泉になる。同時に、自分自身も誰かの学びを刺激する存在になれる可能性がある。
第三に、具体的な目標を設定することだ。例えば「終戦100周年の2045年、73歳の時に昭和史に関する著作を完成させる」といった明確なゴールを定めることで、そこから逆算して学習計画を立てられる。ただし、大切なのは柔軟性を持つことだ。目標は途中で変更してもかまわない。重要なのは、常に前進し続ける姿勢そのものなのである。
現代日本において、一つの興味深い現象が静かに広がっている。それは「資格マニア」と呼ばれる人々の存在である。彼らは資格取得そのものに強い情熱を注ぎ、時には実用性を度外視してでも次々と新しい資格に挑戦し続ける。この現象は単なる個人的な趣味を超[…]
まとめ

大人になって「もう一度学びたい」という思いが芽生えたとき、本書は心強い道しるべとなってくれる。これは単なる体験記ではない。教育現場で働く講師ならではの視点から描かれた、実践的な「学び直し」の指南書だ。一歩を踏み出せずにいる読者に、そっと勇気を与えてくれる一冊である。
勉強と学問の違い、リスキリングとリカレントの区別といった基本的な概念を丁寧に整理したうえで、著者は「どの学びにも優劣はない」と明快に語る。その言葉には説得力がある。著者自身は大学での学び直しを選んだが、本書で示される考え方や実践的なヒントは、大学以外での学びを検討している人々にも十分に役立つ内容だ。
特に注目したいのが第5章「学びの不安に応えるQ&A」である。学び直しを前に抱く様々な不安や疑問に対し、著者が自らの経験をもとに誠実に答えている。これから学びの道を歩もうとする人にとって、具体的な判断材料となる貴重な章だ。自分なりの学びの形を考える際に、きっと参考になるはずである。
概要 「学問のすすめ」は、福沢諭吉が1872年(明治5年)から1876年(明治9年)にかけて発表した17編からなる教育思想書です。初編の冒頭「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」の一節で広く知られ、明治時代に340万部を売り上[…]